広島・宮島口で60年にわたり愛されてきた「おきな堂」が、2025年5月末で閉店することが明らかになりました。
観光客数が過去最多を記録し、インバウンド需要も追い風となるなか──なぜ、あえて歴史に幕を下ろす決断に至ったのでしょうか?
本記事では、
✅「おきな堂」閉店の背景にある本当の理由
✅「クリーム入りもみじまんじゅう」元祖としてのこだわり
✅ 閉店までに間に合う購入方法と注意点
✅ 気になる跡地や今後の動き
について、わかりやすく解説します。
閉店を惜しむ声が高まる今、最後に味わえるチャンスを逃さないよう、ぜひチェックしてみてください。
🏡 宮島口の顔「おきな堂」とは?創業からの歩み

広島県廿日市市、宮島口。
世界遺産・宮島へ渡るフェリー乗り場の目の前で、60年もの間、観光客を迎え続けてきた老舗和菓子店「おきな堂」。
創業は1965年12月。
創業者・木谷善三郎氏のもと、翌年には息子の憲昭さんも加わり、家族で店を守ってきました。
当時は洋菓子ブームの真っ只中。
憲昭さんは近隣のケーキ店に通い、生地作りを研究。
従来のもみじまんじゅうとは一線を画す、スポンジケーキのようにふわふわした生地を完成させました。
さらに、1984年には業界に先駆けて「クリーム入りもみじまんじゅう」を発売。
しっとりやわらかな生地にたっぷりのクリームを包み込んだ革新の味わいは、たちまち人気商品に。
「ふわふわ食感」と「クリームもみじ」という、
今では当たり前となったスタイルを作り上げたパイオニアこそ、「おきな堂」だったのです。
📈 観光客過去最多でも…なぜ閉店?
2024年、宮島を訪れる観光客数は過去最多を記録しました。
新型コロナ禍からの回復とインバウンド(訪日外国人観光客)の急増により、宮島口周辺もかつてない賑わいを見せています。
当然、おきな堂にも連日多くの観光客が訪れ、店内はにぎわいを見せていました。
売上だけを見れば、「絶好調」と言ってもよい状況だったかもしれません。
しかし、それでも「閉店」という選択を余儀なくされたのです。
背景にあったのは、
「ただ売れれば続けられる」という単純な話ではないという現実でした。
おきな堂が大切にしてきたのは、
手作りの味・品質を守り抜くこと。
ふわふわの生地に手作りのあん、そしてクリームを包み込んだもみじまんじゅうは、素材も製法も極めて繊細です。
観光客数が増えることで、
- 商品の回転は早くなる
- 売り上げも一時的には伸びる
一方で、 - 保存・管理のリスクが上昇する
- 品質説明が行き届かない可能性が高まる
といった見えないリスクも急増していきました。
特に、短い消費期限(3日間)にもかかわらず、
外国人観光客や時間に追われる旅行客には保存方法や消費タイミングの説明が難しいという問題が発生。
もしも管理不足で品質が劣化すれば──
たとえ一度でも事故が起これば、
60年守り続けた信頼は一瞬で失われてしまう。
「売れるかどうか」ではなく、
「安心して美味しいものを届けられるか」。
おきな堂は、そこに揺るぎない信念を持っていました。
結果として、
『売上好調』という表面的な波には乗らず、あくまで自らの信条を守る道を選んだ。
それが、閉店という決断につながったのです。
☀️ 暑さが直撃!生菓子ならではの「品質リスク」
おきな堂のもみじまんじゅうは、ふわふわの生地と手作りのあん・クリームが特長です。
そのこだわりが、多くのファンを惹きつけてきた一方で──
実は**「品質管理」という大きな課題**とも常に向き合ってきました。
特に近年は、地球温暖化による夏場の猛暑が深刻化。
生地に多くの水分を含む「生菓子」に近いもみじまんじゅうは、
暑さによって傷みやすくなるリスクが一気に高まっていました。
おきな堂では消費期限を「3日間」としていましたが、
昨夏は初めて、商品に「涼しい場所で保管してください」と書かれたシールを貼り、
日本語と英語で丁寧に注意喚起を始めるなど、必死の対応を続けてきました。
それでも、
- 電車やフェリーの時間を気にして急ぐ観光客
- 日本の高温多湿に慣れていない外国人観光客
に対して、すべてのリスクを伝えきるのは困難。
仮に、持ち運び中に傷んでしまった商品を口にして体調を崩す人が出たら──
「食中毒を出すことなくやってきた60年の歴史」が、そこで途切れてしまうかもしれない。
そんな恐怖と隣り合わせの営業を続けることは、
「お客様に安心して食べてほしい」という信念に反する。
憲昭さんは、そう強く感じたといいます。
品質リスクを背負ってまで続けるよりも、
最高の状態で味わってもらえるうちに、店を閉じる。
その潔い決断が、今回の閉店につながったのです。
💰 物価高と人手不足、そして「ブランド哲学」
おきな堂が直面していた課題は、品質管理のリスクだけではありませんでした。
近年、全国的に進む物価高騰と人手不足の波は、小規模な個人店にも容赦なく押し寄せていました。
材料費は年々上昇し、
もみじまんじゅう1個の価格も10年前と比べて30円〜50円ほど値上げせざるを得ない状況に。
現在の販売価格は1個140円──
それでも「安くて手軽に楽しめる宮島みやげ」というイメージを守るため、
これ以上の値上げは踏みとどまっていました。
一方で、販売価格を抑えたままでは
- 利益率の低下
- 人件費の負担増
- 店舗運営の継続困難
といった問題が徐々に積み重なっていきます。
さらに、熟練の職人技が必要な手作り工程を支える人材の確保も困難に。
機械化や大量生産には頼らず、手作業にこだわってきたからこそ、
簡単に「人を増やせばいい」という話にはならなかったのです。
──それでも、
おきな堂は、ブランドの核を守ることを最優先しました。
「ふわふわで、やさしい味わい」
「できたての美味しさを届ける」
「安くて親しみやすい宮島みやげ」
これらの“当たり前”を犠牲にしてまで、
規模を拡大したり、大量生産型にシフトしたりする道は選ばなかった。
おきな堂が守り続けたのは、
「売り上げ」よりも「信頼」と「想い出」だったのです。
だからこそ、
過去最多の観光客を前にしても──
物価高と人手不足の現実を前にしても──
「品質を保てないのなら、ここで幕を下ろそう」と、潔く決断したのでした。
🛍️ まだ間に合う!「おきな堂」のもみじまんじゅうを食べるなら今

60年にわたって愛され続けた「おきな堂」は、
2025年5月末をもって、惜しまれながらも閉店します。
つまり──
今なら、まだ間に合います。
宮島口のフェリー乗り場近く、
変わらない笑顔で迎えてくれる「おきな堂」の店舗には、
今日もふわふわの生地とやさしい甘さのもみじまんじゅうが並んでいます。
おきな堂のもみじまんじゅうは、
- 生菓子に近い繊細な食感
- できたてならではの、しっとり感と香ばしさ
が最大の魅力。
閉店後は、もう二度とこの味を味わうことはできません。
購入する際には、店頭での保管方法の案内にしっかり耳を傾け、
できるだけ当日中、遅くとも翌日中には召し上がるのがおすすめです。
とくに人気の「クリーム入りもみじまんじゅう」は、
おきな堂が元祖を誇る看板商品。
売り切れることも多いため、早めの時間帯に訪れると安心です。
📍 おきな堂へのアクセス

- 住所:広島県廿日市市宮島口1丁目(宮島フェリーターミナルすぐ)
- 最寄り駅:JR宮島口駅 徒歩約3分
- 営業時間:10:00〜18:00頃(売り切れ次第終了)
- 定休日:なし(閉店まで無休予定)
※訪問前には公式情報の最新状況を確認することをおすすめします。
“今しか手に入らない特別な味”を求めて、
ぜひ、おきな堂最後の日々を見届けてみませんか?
🏢 おきな堂跡地はどうなる?宮島口エリアの今後
気になるのは、「おきな堂」が閉店したあとの跡地がどうなるのか──という点です。
現時点(2025年4月時点)では、
おきな堂跡地に関する公式な発表はありません。
しかし、周辺状況を見渡すと、
宮島口エリアは今、大きな変化の只中にあります。
- 新しいフェリーターミナルビルの整備
- インバウンド需要に対応したカフェ・レストランの進出
- 観光客向けの宿泊施設やお土産店の新規出店
こうした流れを見ると、
おきな堂跡地にも今後、
「観光客ニーズに応える新たなテナント」が入る可能性が高いと予想できます。
たとえば、
- 土産物を扱う和風カフェ
- テイクアウト対応のスイーツショップ
- 宮島ならではの体験型施設(焼き体験、食体験など)
といった業態が候補に上がるかもしれません。
一方で、
60年もの間「おきな堂」が守ってきた、
この場所の「懐かしさ」や「温もり」を失ってほしくない──
そんな声も地元では聞かれています。
新たな店舗が入るにせよ、
おきな堂が築いてきた温かな空気感を、
次の世代にも受け継いでほしいと願うばかりです。
跡地の動向については、
今後も情報が入り次第、随時更新していきます。
まとめ|守り続けた想いとともに、静かに幕を下ろす「おきな堂」
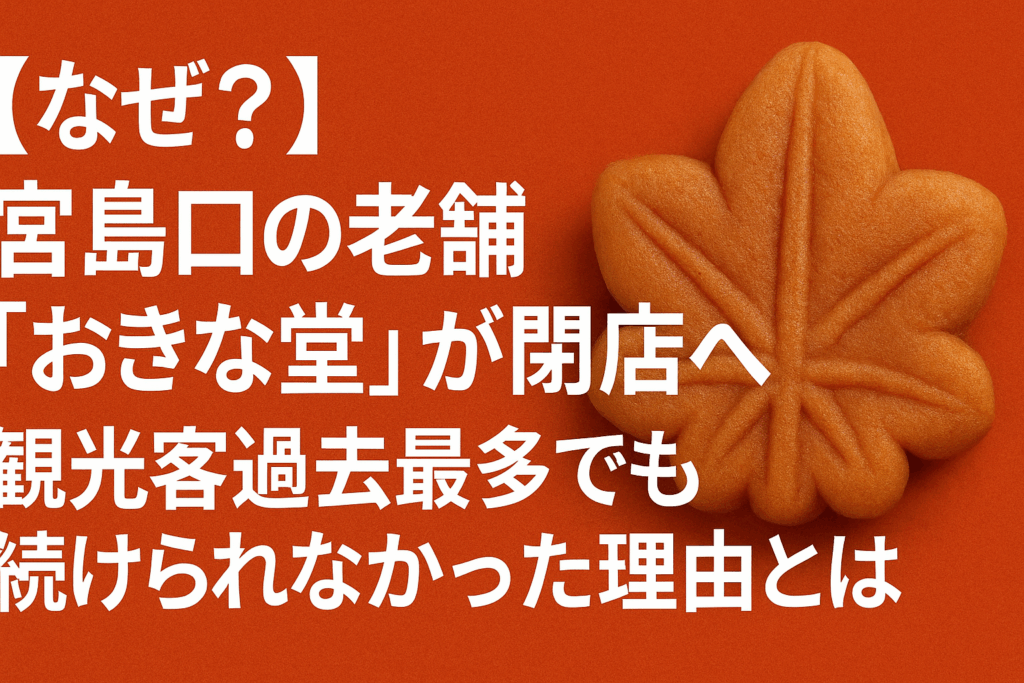
60年という長い時を、宮島口の玄関口で見守り続けた「おきな堂」。
観光客が過去最多を記録するなかでも、
“売れるから続ける”のではなく、
“安心して食べてもらえる品質を守る”ために、静かに店じまいを決断しました。
暑さによる品質リスク、物価高、人手不足──
多くの課題を前にしても、最後までブレることなく、
「ふわふわでやさしいもみじまんじゅう」というブランド哲学を貫いた姿勢には、
多くの人の心を打つものがあります。
まだ「おきな堂」の味を体験できる時間は残されています。
閉店までの限られた日々、
あの懐かしくも新しいもみじまんじゅうを、
ぜひあなた自身の思い出に刻んでみてください。



