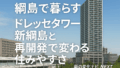「旧車に乗り続けると自動車税が高くなるのはなぜ?」──
13年以上経過した車に課せられる“自動車税の重課制度”に、多くのドライバーから不満の声が上がっています。環境負荷への対策として導入された制度とはいえ、「物を大切にすることが罰になるのか」と疑問を抱くユーザーも少なくありません。
本記事では、旧車に課せられる税制の仕組みや他国との比較、実際の負担額、軽減対策、そして世論の動きまでを徹底解説。
旧車とこれからも賢く付き合っていくためのヒントを、わかりやすくお届けします。
[quads id=1]
なぜ旧車の自動車税は高すぎるのか?【制度の背景と問題点】
旧車に対する自動車税が「高すぎる」と感じられるのは、13年を超えた車に対して課される“重課制度”に原因があります。これは環境負荷を理由にした税制上の措置ですが、多くのユーザーにとっては理不尽に映る制度設計です。
この制度の背景には、日本政府が掲げる環境政策の一環として「低燃費・低排出ガス車への移行を促す」目的があります。古い車は最新の車両に比べてCO2排出量が多く、燃費効率も悪いため、税制面で“環境負荷”の代償を払わせる形になっています。実際、自家用のガソリン車の場合、13年を超えるとおおよそ15%増の自動車税が課され、ディーゼル車ではさらに高い20%超となることもあります。
たとえば1.5リットルクラスの普通車(ガソリン)の自動車税は、通常で34,500円ですが、13年超の旧車になると39,600円に上がります。5,000円以上の差は年間コストとしても無視できません。また、毎年5月にはこの通知が届くため、ユーザーは納税のたびに制度への不満を抱えるのが実情です。
環境政策としての意図は理解できるものの、日頃から車を丁寧に維持しているユーザーにとって「長く乗るほど罰金を科されるような制度」は不公平と感じられて当然です。そもそも排ガス検査や車検などをクリアしている車に対して、さらに税金を加える現行制度には見直しの余地があると言えるでしょう。
13年以上の旧車に課される“重課”の具体的な内容とは?
13年以上経過した自動車には、通常よりも高い税率が適用される「重課制度」が導入されています。これは“環境負荷が高い車に対するペナルティ”という位置付けで、車種や燃料種別ごとに異なる重課率が課されます。
自動車税の重課は、一定年数を経過した車の環境性能が相対的に劣化していることを根拠に設定されています。具体的には、ガソリン車で新車登録から13年を経過すると、自動車税の税率が約15%増しに。ディーゼル車ではさらに厳しく、18年経過で約20%の重課率となります。また、重量税についても同様に加算されるため、旧車ユーザーの負担は二重三重に増す仕組みになっています。
たとえば、排気量1.5Lのガソリン車の場合、13年未満なら34,500円であるところが、13年以上経過すると39,600円に上昇します。さらに車検時に支払う重量税も同時に重課され、2年分で11,400円から15,000円前後に跳ね上がることもあります。これにより、年間コストで1万円近い追加出費が発生するケースも少なくありません。
この重課制度は、単なる環境施策の一環にとどまらず、旧車ユーザーにとって実質的な経済的プレッシャーとなっています。とくに家計に余裕がない中で車を長く使い続けている人々にとっては、大きな負担です。現状を正確に理解し、今後の維持方針や乗り換え時期を検討する材料として、制度の詳細を押さえておくことが重要です。
他の先進国と比べて、日本の旧車課税は本当に異常?

日本の旧車に対する自動車税の課税方法は、他の先進国と比べて“異常”といっても過言ではありません。多くの国では、旧車文化を保護・奨励する傾向があり、日本のように年数を重ねた車に対して一律で課税を重くする制度はむしろ珍しい存在です。
欧米諸国では、旧車(クラシックカー・ヒストリックカー)を文化的・技術的な遺産と捉え、維持・保存する方向性が強く打ち出されています。たとえば、
- ドイツ:30年以上前の車両に対しては「Hナンバー」制度を設け、年間税額を一律化(約200ユーロ程度)し、維持費を抑える政策を採用。
- イギリス:40年以上前の車両は自動車税が免除。MOT(車検)も免除対象となる。
- アメリカ(カリフォルニア州など):クラシックカー登録により税制優遇やレストア支援が受けられる。
一方の日本は、古い車を維持しているというだけで増税され、文化的価値や整備状態は考慮されません。整備を怠るわけでもなく、むしろ大切に乗っているユーザーにも一律でペナルティを科すこの制度は、世界的に見ても異質な仕組みです。
日本では13年を超えた時点でガソリン車は15%、ディーゼル車は20%以上の増税という明確なペナルティが適用されます。しかしドイツのように“文化財”として扱われる制度がある国と比較すると、「税の役割が文化支援か排除か」という根本的な違いがあることがわかります。
日本の旧車課税制度は、欧米先進国と比較してもかなり厳しい部類に入ります。もし今後、自動車文化や環境保全の両立を図るのであれば、「状態の良い旧車には優遇を」「趣味性の高い車両は文化的価値として保護を」といった柔軟な制度設計が必要でしょう。今の制度は、単に古いという理由だけで一律に課税強化する“画一的なやり方”に終始しており、国際的な潮流とは乖離していると言えます。
税負担が重い旧車を持ち続けるメリットとデメリット
旧車を所有し続けることには、たしかに自動車税などのコスト的なデメリットが存在しますが、それでも「味」「愛着」「構造のシンプルさ」など、現行車にはない魅力や実用的なメリットも多く存在します。メリットとデメリットを整理することで、旧車との付き合い方を再考するきっかけになります。
旧車を持ち続けることで最も大きな課題は、やはりコストの増加です。前述のとおり、13年を超えた車には自動車税の重課、重量税の加算が適用され、さらに修理・部品交換の頻度も増えてきます。一方で、旧車には新車にはない「メンテナンス性の良さ」や「趣味性の高さ」「減価償却済みゆえの経済的利得」などのメリットも見逃せません。
たとえば、2005年式の国産セダンを所有しているケースでは、購入費用はすでにゼロに近く、車両保険も安く抑えられています。DIYで整備できる構造の簡易さに魅力を感じているユーザーも多くいます。また、初期費用をかけずに乗り続けられるという点で、「新車の購入にかかるローン負担を避けたい」という家庭層にも根強い支持があります。
デメリットの側面:
- 重課による税金増(年間5,000円〜10,000円増)
- 車検や整備費用の増大(経年による部品劣化)
- 故障時の部品入手が困難(とくに海外車や一部国産車)
- 保険料が割高になるケースも(車両区分や年代により)
メリットの側面:
- 購入費が安く済む(もしくはすでに支払い済)
- シンプルな構造で整備しやすく、DIYに向く
- 趣味性・希少性が高く、愛着がわく
- 買い替えの必要がない分、環境負荷はむしろ少ないという見方も
税金面のデメリットは確かにありますが、それを補って余りあるほどの「所有満足感」や「コストパフォーマンス」を旧車は提供してくれる場合があります。重要なのは、どのようなライフスタイルを送りたいか、自動車に何を求めるかという視点で判断することです。自分にとっての最適な選択が何か、コストと価値を天秤にかけて考えることが必要です。
重課を回避・軽減するためにできる5つの対策

旧車に課される自動車税の重課を完全に免れることは難しいですが、いくつかの工夫や制度を活用することで、その負担を軽減する方法は存在します。代表的な対策を5つ紹介します。
税制は法律に基づいて定められているため、直接的な免除は難しいものの、車の使い方や登録区分、整備状況、所有方法などを工夫することで、間接的に税負担を抑えることが可能です。以下は、多くの旧車ユーザーが実践している現実的な方法です。
具体例・対策:
① 使用頻度が低いなら「一時抹消登録」 一時的に車を使わない場合、ナンバーを返納し「一時抹消登録」を行うことで、自動車税の課税対象外となります。再び使用する際は再登録が必要ですが、趣味用途や季節限定利用の旧車には有効です。
② 軽自動車や排気量の小さい旧車へ乗り換える 軽自動車は13年超であっても自動車税は割安で、重課額も小さめです。また、排気量の小さい普通車も税率が抑えられるため、乗り換えによる節税効果が期待できます。
③ クラシックカー登録制度を活用(自治体・地域限定) 一部自治体では、一定年数以上の旧車に対して税制優遇を行う制度があります。全国的な制度ではないため地域差はあるものの、事前に自治体に問い合わせる価値はあります。
④ 法人名義への変更を検討する 用途や職種によっては、法人で所有することで節税メリットが出る場合もあります。ただし、法人税務や損金計上ルールの理解が必要で、税理士への相談が推奨されます。
⑤ 車検のタイミングを見直す 車検と重量税の支払いタイミングを工夫することで、一時的に負担を平準化することが可能です。車検業者の中には、重量税の納税月ずらしに対応してくれるケースもあります。
「重課だから仕方がない」とあきらめるのではなく、制度の仕組みを理解した上で、自分に合った節税・軽減策を選ぶことが大切です。特に旧車に強いこだわりを持つ方ほど、こうした工夫によって愛車との付き合いを長く続けていけるでしょう。
旧車ユーザーの怒りと世論の動き|制度見直しの可能性は?
旧車に対する重課制度に対しては、年々多くのユーザーから不満の声が上がっており、SNSや署名運動を通じて制度見直しを求める動きも強まりつつあります。政治や業界団体の一部もこうした声に反応し始めており、今後制度が見直される可能性はゼロではありません。
旧車重課制度が導入された当初と比べて、現在は車両のメンテナンス技術も向上しており、「古い=環境負荷が高い」という単純なロジックが通用しにくくなっています。実際、定期的に整備された旧車は排ガス規制をクリアし、現行車に匹敵する性能を維持しているケースも少なくありません。
また、SNSやブログなどでの不満の可視化が進んだことにより、
- 「物を大事にして乗っている人が損をするのはおかしい」
- 「買い替えを強制するような税制は時代遅れ」 といった意見が市民レベルで共有され、署名活動や意見投稿などの具体的なアクションに繋がっています。
近年では、日本自動車連盟(JAF)などが重課制度の見直しを求める意見を国土交通省に提出したこともあり、メディアでも取り上げられました。さらに、SNS上では「#旧車税制見直し」「#重課廃止」などのハッシュタグが多く使われるようになっており、関心の高まりがうかがえます。
国会質問でも旧車税制に関する質疑が取り上げられるケースが出てきており、政治的なアプローチが始まっている兆しも見られます。ただし、制度変更には国全体の税収構造や環境政策との整合性も求められるため、即時の大幅な改正は難しいのが現状です。
旧車ユーザーの声が可視化され、一定の世論形成がなされつつある今こそ、制度見直しへの働きかけが効果を持つタイミングかもしれません。SNS投稿や署名活動、JAFなどへの意見提出といったアクションを通じて、粘り強く制度変更の必要性を訴えていくことが求められます。社会全体で「モノを大切にする人が報われる制度」へと移行するには、ユーザーの声がカギとなるでしょう。
[quads id=1]
まとめ|今後も旧車と賢く付き合うには
旧車に課せられる自動車税の重課制度は、経済的に大きな負担である一方、旧車ならではの魅力や所有する価値も根強く存在します。重要なのは、制度の仕組みを理解した上で、自分のライフスタイルや価値観に合った付き合い方を選ぶことです。
日本の旧車課税制度は環境政策の一環として導入されたものですが、現代の整備技術や車両性能を鑑みれば、必ずしも「古い=悪」とは言い切れない状況です。ユーザー側が賢く制度を理解し、負担を軽減しながら愛車と付き合っていく姿勢が問われています。
具体例・提案:
- 重課制度の内容を正確に把握し、納税額の見通しを立てておく
- 一時抹消や軽自動車などの節税方法を検討する
- クラシックカー登録制度や地域の優遇措置を活用する
- オーナー同士のネットワークやSNSで情報共有を行う
- 制度への意見提出など、改善への声を届ける努力を続ける
旧車との付き合いには“費用”と“価値”のバランスが不可欠です。「税金が高すぎる」という不満だけでなく、自分の車に何を求めるのかを再確認することが、後悔しない選択へとつながります。制度への問題提起は必要ですが、それと同時に、自らの行動や選択によって「旧車と上手に生きる道」を見つけることもまた重要なのです。
[quads id=1]