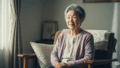松戸市松戸新田で60年にわたり地域に愛されてきた銭湯「松戸ヘルスランド」が、2025年8月3日をもって閉店します。昭和40年から続く歴史ある銭湯の閉鎖は、長年の常連客はもちろん、サウナ愛好家や地域住民に大きな衝撃を与えています。
今回の記事では、この閉店のニュースを受け、皆さんが次に気になるであろう情報を深掘りしていきます。松戸ヘルスランドの閉店理由からその歴史、そして気になる閉店後の跡地の行方、さらには松戸に残る銭湯の現状と、失われゆく日本の銭湯文化の未来について詳しく解説します。
[quads id=1]
松戸ヘルスランド 閉店の背景と、その歴史

まずは、今回の閉店に至った経緯と、松戸ヘルスランドが歩んできた60年について詳しく見ていきましょう。
突然の閉店、その直接的な理由は?
松戸ヘルスランドの閉店は、設備の故障が直接の引き金となりました。今年4月末、浴槽にお湯がたまらなくなるという事態が発生。
現在は一時的に修復され浴槽は使える状態にはありますが、根本的な修理にはなんと億単位の費用がかかることが判明したのです。
老朽化が進んだ設備の全面的な改修となると、配管の入れ替えやボイラーの刷新など大規模な工事が必要となり、その費用は想像を絶します。
経営を続ける上で、この巨額な投資は現実的ではないと判断せざるを得なかった、と店主の高橋由利子さんは語っています。長年地域に貢献してきた銭湯が、まさに「寿命」という形で幕を閉じることになったのです。
「源湯」から「松戸ヘルスランド」へ — 60年の歴史を振り返る
松戸ヘルスランドは、1965年(昭和40年)に「源湯(みなもとゆ)」として産声を上げました。初代店主である高橋さんの祖父「源之助」さんの名前がその由来です。当時の松戸にはまだ多くの銭湯が存在し、地域の人々の暮らしに欠かせない社交場でもありました。
平成の初めごろ、先代である高橋さんの父親が店を大規模リフォームした際に、現在の「松戸ヘルスランド」というユニークな店名に変更しました。
この名前には、「店の所在地『松戸』、入浴は健康に良いので『ヘルス』、そしてディズニーランドのように人がたくさん集まる店にしたいと『ランド』」という思いが込められていました。
高橋さん自身は「いかがわしい店のような名前」と当時を振り返り、別の名前に変えたかったそうですが、近年ではSNSで面白がって話題にしてくれるお客さんが増え、「このままでもいいと思うようになった」と笑顔で語っています。
このリフォームは単なる改名に留まらず、松戸市内の銭湯では初の試みとなるサウナやジャグジーの設置、さらには24時間営業、年中無休という画期的な営業形態への転換も行われました。
この英断が功を奏し、「近くにスーパー銭湯ができるまでの数年間がいちばん繁盛していた」と高橋さんは懐かしんでいます。
当時の松戸ヘルスランドは、まさに時代を先取りしたモダンな銭湯として、多くの人々で賑わっていたことでしょう。
利用者の声|SNS・口コミから抜粋
「うわ~ お世話になった銭湯が…寂しい」
— 千葉労連の広場(Xより)
「松戸ヘルスランドが8月で閉店。ぼくは勝手に『松戸のしきじ』と呼んでいた。残念だ。」
— Instagramより(投稿者:坂田恭造さん、2025年6月7日)
「3段の遠赤外サウナの湿度高めで少しすると沢山汗が…天然地下水も掛け流しで気持ちよかった」
— サウナ愛好家の記録(sauna-ikitai.comより)
閉店への思い — 店主・高橋由利子さんのメッセージ
高橋さんは、何十年も毎日利用する常連さん、市場関係や飲食関係の仕事の前後に利用する人、そして近年ブームとなっているサウナ目的で遠方から訪れる人など、本当に様々な人々が松戸ヘルスランドを利用してくれたことに感謝の気持ちを述べています。
「急なことだったので、閉店後についてはまだ何も決まっていない。建物を残すかどうかも含めて未定」と語る高橋さん。長年経営してきた店との別れは、想像以上に心苦しいことでしょう。
それでも、「閉店まで変わらず来てもらえたら」と、最後の最後まで変わらぬ愛情で利用客を迎え入れる姿勢を見せています。松戸ヘルスランドは、単なるお風呂屋さんではなく、地域の人々の生活の一部であり、心の拠り所だったことが伺えます。
[quads id=4]
松戸ヘルスランド閉店後、建物はどうなる?跡地利用の可能性
多くの人が気になるのは、閉店後の建物の行方ではないでしょうか。現時点では未定とされていますが、考えられる可能性を探ります。
建物存続か、解体か — 現在の状況と今後の見通し
高橋さんが語るように、閉店後の松戸ヘルスランドの建物について「まだ何も決まっていない」というのが現状です。億単位の費用がかかる修理を断念した以上、現状の銭湯として営業を続けることは困難です。
考えられる選択肢は大きく分けて二つ。一つは建物の解体です。築60年にもなる建物は老朽化が進んでおり、大規模な修繕を要する状態です。
解体費用も決して安くはありませんが、更地にして売却する方が土地としての価値が高まる可能性があります。もう一つは、建物を残し、全く別の用途で再利用することです。
しかし、銭湯という特殊な構造から、大幅なリノベーションが必要となり、ここにも多大なコストがかかります。立地条件や建物の状態、そして所有者の意向が、今後の行方を大きく左右するでしょう。
跡地利用のシナリオ — 地域への影響は?
もし建物が解体され、更地になった場合、最も可能性が高いのはマンションやアパートなどの住宅施設としての再開発です。松戸市は都心へのアクセスも良く、住宅需要は一定数存在します。また、近隣に生活利便施設が少ない場合は、小規模な商業施設や医療施設などが建設される可能性も考えられます。
いずれのケースにせよ、長年地域に親しまれてきた銭湯がなくなることは、周辺住民の生活に少なからず影響を与えるでしょう。日常的な入浴施設がなくなるのはもちろんのこと、地域コミュニティの拠点が一つ失われることにもなります。
もし建物が残る場合、そのユニークな構造を生かしてカフェやレストラン、あるいは複合施設などに生まれ変わる可能性もゼロではありません。しかし、これは初期投資や運営面でのハードルが高く、実現には強いビジョンと資金力が必要となるでしょう。
[quads id=4]
松戸市内の銭湯は残り3店舗に — 今後、銭湯文化はどうなる?
松戸ヘルスランドの閉店により、松戸市内に現存する銭湯は4店舗から3店舗に減少します。これにより、地域の銭湯文化にどのような影響があるのでしょうか。
松戸市内の現存銭湯リストとそれぞれの魅力
松戸ヘルスランドの閉店後、松戸市内で営業を続ける銭湯は以下の3店舗となります。それぞれの銭湯が持つ独自の魅力に目を向けてみましょう。
- 寿湯(ことぶきゆ):松戸市内の中心部に位置し、昔ながらの銭湯の雰囲気を色濃く残しています。
- 新松戸温泉 湯らんの里:天然温泉を売りにした、比較的新しいタイプの銭湯で、露天風呂や多様な浴槽が人気です。
- 平和湯(へいわゆ):地域密着型の銭湯で、地元の人々に長年愛され続けています。
これらの銭湯は、それぞれ異なる特色を持っています。松戸ヘルスランドの閉店は残念ですが、残る3店舗がこれからも地域の人々の憩いの場として、銭湯文化を守り続けてくれることを願うばかりです。
失われゆく銭湯文化 — その背景と未来
松戸市に限らず、日本全国で銭湯の減少は深刻な問題となっています。ピーク時には全国で2万軒以上あった銭湯は、現在では2000軒を割り込むほどに激減しました。
その背景には、建物の老朽化や設備の陳腐化、後継者不足、そして家庭風呂の普及やスーパー銭湯・温浴施設の台頭といった様々な要因が複雑に絡み合っています。
銭湯は、単にお風呂に入る場所というだけでなく、地域のコミュニティを形成する重要な役割を担ってきました。
近所の人々との交流の場であり、情報交換の場であり、子どもたちにとっては初めての公共の場体験の場でもありました。
銭湯がなくなることは、地域の「裸の付き合い」が失われることでもあり、寂しさを感じる人も少なくありません。
しかし、一方で「リノベーション銭湯」や、若い世代による銭湯文化の再評価の動きも見られます。伝統を守りつつ、現代のニーズに合わせた新しい銭湯の形が模索されています。松戸に残る銭湯も、こうした新しい風を取り入れながら、これからも長く愛される存在であり続けてほしいものです。
[quads id=4]
最終営業日まで残りわずか — 最後に訪れるには?
閉店は2025年8月3日。松戸ヘルスランドとの別れを惜しむために、最後に訪れたいと考えている方も多いのではないでしょうか。
営業時間・料金の再確認
- 営業時間:午前6時~午前9時、正午~午後11時(最終受け付けは午後10時30分)
- 料金:
- 大人:500円
- 中学生:300円
- 小学生:170円
- 幼児:70円
- 追加サウナ(貸タオル付き):650円
アクセス方法
松戸ヘルスランドは、新京成線「松戸新田駅」から徒歩圏内に位置しています。詳細はGoogleマップなどでご確認ください。駐車場については、事前に店舗へ問い合わせるのが確実でしょう。
店主からのメッセージと、訪問者への呼びかけ
高橋さんは「閉店まで変わらず来てもらえたら」と呼びかけています。長年にわたる感謝の気持ちを伝えるためにも、ぜひ最後に松戸ヘルスランドを訪れて、その温かい湯と雰囲気を心に刻んでください。そして、SNSなどで思い出や感謝の気持ちを共有し、松戸ヘルスランドが歩んできた60年の歴史を多くの人と分かち合ってみてはいかがでしょうか。
松戸ヘルスランドの閉店は、一つの時代の終わりを告げる寂しいニュースですが、これもまた街の変化の一つです。この閉店を機に、私たちが暮らす地域の銭湯文化について、改めて考えてみるきっかけになれば幸いです。
[quads id=4]