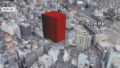銀座に志かわ 閉店?栄枯盛衰の舞台裏。熱狂の終焉、そして疑問。かつて2010年代後半、日本中を席巻した「高級食パンブーム」。1本1000円近い食パンに行列ができ、飛ぶように売れる光景は日常となりました。しかし、その熱狂は長くは続かず、「銀座に志かわ」が140店舗から50店舗に、他の多くの専門店も大量閉店へと追い込まれるという現実に直面しています。なぜあれほどまでに人々を惹きつけ、短期間で急拡大したブームは、なぜあっという間に収束してしまったのでしょうか?単なる一時的な流行として片付けられない、その深層に迫る疑問が今、投げかけられています。
銀座に志かわ 閉店?高級食パンブーム、その「必然」の背景

高級食パンブームの盛り上がりには、いくつかの複合的な要因が絡み合っていました。
消費者の「プチ贅沢」と「手土産需要」
まず、消費者の心理に響いたのが「プチ贅沢」としての魅力です。日々の暮らしの中で、少しだけ上質なものを手に入れることで得られる幸福感は、高価格帯の食パンが提供する価値と合致しました。また、その美しい見た目や話題性から、「気の利いた手土産」としても重宝され、贈答品としての需要もブームを後押ししました。
「異業種参入」を促したビジネスモデル
ブームが急速に拡大した背景には、そのビジネスモデルの参入障壁の低さがありました。一般的なベーカリーが多種多様なパンを扱うのに対し、高級食パン専門店は食パン一点に特化することで、店舗運営のオペレーションを大幅に簡素化できました。これにより、製造工程や発注管理が複雑にならず、比較的高い利益率が見込めたのです。さらに、セントラルキッチンで冷凍生地を用意できれば、効率化も図れるという点も、異業種からの参入を促す大きな要因となりました。浄水器メーカーであるOSGコーポレーションが「銀座に志かわ」を立ち上げたように、本業で培ったノウハウやネットワークを活かし、多くの企業がこの市場に参入しました。
メディアが作り出した「熱狂」の正体
そして、ブームを爆発的に加速させたのがメディアの存在です。「銀座食パン戦争」や「東西食パン大戦争」といったキャッチーなフレーズが意図的に打ち出され、テレビの経済番組、ワイドショー、バラエティ番組などで連日のように取り上げられました。
特に「ガイアの夜明け」のような人気番組での特集は、消費者の関心を一層煽り、店舗への行列をさらに長くしました。
メディアは、高級食パンの「とろける食感」「ふわふわの生食パン」といった特徴を強調し、その希少性や話題性を巧みに演出しました。
テレビ番組では、芸能人が試食して絶賛する姿が映し出され、視聴者は「自分も食べてみたい」「あの行列に並んでみたい」という強い購買意欲を刺激されました。
また、雑誌やウェブメディアでも「行列のできる店」「幻の食パン」といった見出しが踊り、SNSでは購入した食パンの写真を投稿する人々が溢れました。
こうした多角的なメディア露出は、消費者の間で「乗り遅れてはいけない」という心理(FOMO:Fear Of Missing Out)を生み出し、ブームは自己増幅的に拡大していったのです。事業者、メディア、そして視聴者が一体となって「ブーム」という渦を作り出し、あれよあれよという間にトレンドは過熱していったのです。
銀座に志かわ 転換点:ブーム収束の「必然」と課題
しかし、過熱したブームは、その裏側に多くの課題を抱えていました。
「レア感」の消失と競争激化
店舗数の急増は、高級食パンの「レア感」を薄める結果となりました。当初は限られた店舗でしか手に入らない「特別な一品」であった高級食パンが、瞬く間に全国各地に広がり、どこでも手に入るようになったことで、その希少性は急速に失われました。
消費者の間では、「わざわざ行列に並んで買うほどのものか」という意識が芽生え始め、特別感は薄れていきました。さらに、多くのブランドが似たような「ふわふわ」「しっとり」「甘い」といった特徴を打ち出し、同じような価格帯で販売したため、個々のブランドが差別化を図ることが極めて困難になったのです。
結果として、消費者はどの店の食パンも大差ないと認識し、購入の動機が薄れていきました。
外部環境の変化が追い打ちに
追い打ちをかけるように、外部環境の変化が経営を圧迫しました。コロナ禍による外出自粛や行列制限は、購買意欲を減退させ、ブームの熱狂を冷ます大きな要因となりました。さらに、ロシアとウクライナ間の戦争による小麦価格の高騰は、原材料費を直撃し、多くの店舗の採算を大幅に悪化させました。
「単一商品」の限界
食パン一点突破という戦略は、製造工程の単純化や品質管理の集中により、ブーム初期の急速な拡大を支える強みとなりました。
しかし、長期的に見ると、この戦略は大きな脆弱性へと転じました。消費者は、どのブランドも似たような「ふわふわ」「しっとり」「甘い」といった特徴に終始するため、「味が単調で飽きてしまう」という声が聞かれるようになりました。
高価格にもかかわらず「原価が安いのでは?」という疑念も生じ、価格に見合う価値への疑問が浮上。これにより、物珍しさが薄れると購買頻度が低下し、多様な食のニーズ(例えば、食事パンとしての利用や、異なる風味への要望など)に対応できない限界が露呈しました。
他の商材で売上を補えないため、経営が苦しくなると不採算店舗の徹底的な見直し、ひいては閉店を迫られることになったのです。
フランチャイズビジネスの闇とブランドイメージの低下
特に深刻だったのが、フランチャイズビジネスにおける問題です。ブームに乗じて急速に店舗数を拡大した多くのブランドは、フランチャイズ方式を採用しました。これは、本部が初期投資を抑えつつ、短期間で全国展開を進める上で非常に有効な手段でしたが、その裏には多くの課題が潜んでいました。
「乃が美」で取り沙汰された本部とフランチャイジー間の「泥沼訴訟」は、その典型例です。加盟店側からは、本部の過度な出店推進によって市場が飽和し、売上が見込みを下回ったにもかかわらず、高額なロイヤリティや違約金が課せられたことへの不満が噴出しました。経営に行き詰まったフランチャイジーが、ロイヤリティの引き下げや契約解除時の違約金撤廃などを求めて本部を訴える事態に発展し、これは業界全体にネガティブな印象を与えました。
こうしたトラブルは、単に個別の企業間の問題に留まらず、フランチャイズビジネス全体の信頼性を揺るがし、消費者のブランドイメージ低下にも繋がりました。「あの高級食パンの店、実は経営が苦しいらしい」「訴訟問題になっている」といった噂は、商品の品質やブランドへの信頼感を損ない、結果として客足の減少を招く悪循環を生み出したのです。本部の過度な出店推進と、それに伴う加盟店との軋轢は、ブームの終焉を加速させる一因となりました。
銀座に志かわ 生き残ったブランドの「今」と「これから」
多くの高級食パン専門店が閉店を余儀なくされる中、一部のブランドは生き残りをかけて変化を遂げています。
「銀座に志かわ」の現状と戦略転換
「銀座に志かわ」もまた、約140店舗から50店舗前後へと大幅な縮小を余儀なくされました。これは、単なる店舗数の減少に留まらず、ブーム終焉後の市場環境に適応するための痛みを伴う変革を意味します。しかし、同社は生き残るために、商品ラインナップの見直し、販売戦略の転換、そして店舗形態の多様化などを積極的に進めていることでしょう。
具体的には、主力商品である食パンの品質を維持しつつも、季節限定のフレーバーや、食パンに合うジャム、スプレッドといった関連商品の開発・販売を通じて、顧客の飽きを防ぎ、新たな購買機会を創出している可能性があります。
また、かつてのような「行列」に頼る販売戦略から脱却し、オンラインストアの強化、サブスクリプションモデルの導入、あるいは他業種とのコラボレーションによる販路拡大など、多角的なアプローチを試みていることも考えられます。
店舗形態においても、一等地の大型店から、より地域に根差した小型店舗へのシフトや、カフェスペースを併設した複合型店舗の展開など、顧客の利便性向上と運営コストの最適化を図っているかもしれません。
OSGコーポレーションの湯川社長が語る今後の展望や、ブランド維持への覚悟は、単なる売上回復に留まらず、高級食パン市場における確固たる地位を再構築しようとする強い意志を示すものです。
ブームを経験した企業が、いかにして一時的な流行に終わらず、本質的な価値を提供し続ける持続可能なビジネスモデルを構築しようとしているのか、その動向は注目に値します。
その他の生き残りブランド
「高級食パン 嵜本(現SAKImoto bakery)」も約40店舗から14店舗に縮小するなど、各ブランドが厳しい状況に直面しながらも、それぞれが独自の方向性を模索しています。ブームが去った後も存在し続けるブランドは、単なる話題性だけではない、本質的な価値を提供できていると言えるでしょう。
「ブーム」で終わらせないための教訓
高級食パンブームの栄枯盛衰は、タピオカドリンクや唐揚げ、マリトッツォなど、一過性のブームで終わる事例に共通する重要な教訓を与えてくれます。
第一に、一時的な話題性だけに頼らず、本質的な商品力と顧客体験の重要性を再認識することが不可欠です。ブーム初期の「珍しさ」や「行列」は集客に貢献しますが、それだけでは消費者の飽きを招き、継続的な購買には繋がりません。真に顧客に選ばれ続けるためには、味の安定性、厳選された原材料へのこだわり、独自の食感や風味の追求といった「商品そのものの力」が何よりも重要であり、これが欠けていればブームは長続きしないでしょう。さらに、店舗での心地よい接客やパッケージ、オンラインでの情報提供など、購入前後の顧客体験全体がブランド価値を形成し、リピートに繋がることを忘れてはなりません。
第二に、市場の変化に柔軟に対応し、多角化や変化への適応能力を持つことの必要性です。単一商品に依存するビジネスモデルは、市場のトレンド変化や競合の出現に対して非常に脆弱です。ブームが去った後も生き残り、持続的な成長を遂げるためには、コア商品の品質を維持しつつも、関連商品の開発や新たな業態への挑戦など、周辺領域への展開や価値提案の多様化が求められます。
第三に、フランチャイズビジネスにおいては、本部と加盟店が健全な関係を築き、共に成長していくことが不可欠です。フランチャイズは急速な店舗拡大を可能にする強力な手段ですが、本部の一方的な利益追求や、加盟店への過度な負担は、関係破綻とブランド全体の失墜を招きます。長期的な成功のためには、市場飽和を考慮した適切な出店計画や、加盟店への継続的な経営サポートが本部には求められ、相互の信頼と協力が持続的な成長へと繋がるでしょう。
まとめ:銀座に志かわ 消費者が求める「価値」とは
高級食パンブームは、メディアの力と異業種参入の容易さが生み出した熱狂の典型例でした。しかし、ブームが去った後も消費者が本当に求めているのは、単なる「高級」という冠だけではありません。本物の品質、飽きのこない味、そして信頼できるブランドが提供する価値です。
ブームの終焉は、消費者が表面的な流行や一時的な話題性だけでは満足しないという明確なメッセージを突きつけました。彼らが最終的に求めるのは、日常の食卓に彩りを与え、心を満たすような、確かな「価値」なのです。これは、単に高価であることや、特定の原材料を使っていることだけを指すのではありません。例えば、毎日食べても飽きないようなバランスの取れた味わい、健康志向の高まりに応える素材選び、あるいはアレルギー対応など、消費者の多様なニーズに応える柔軟性も含まれるでしょう。
一過性のトレンドから学び、持続可能なビジネスモデルを構築すること。それは、単に売上を追求するだけでなく、顧客との長期的な関係性を築き、ブランドへの愛着を育むことに他なりません。次世代の食パン、そしてあらゆる商品に求められる「価値」の本質は、常に変化する消費者の期待に応え、期待を超える体験を提供し続けることにあると言えるでしょう。