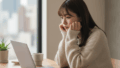まず、読者の皆さまが一番気になっている事実からお伝えします。長年、地域の方々に愛されてきた京都の「髙島屋洛西店」と大阪の「髙島屋堺店」が、2026年にその長い歴史に幕を下ろすことが発表されました。このニュースに、驚きや寂しさを感じている方も多いのではないでしょうか。
「子どもの頃、屋上で遊んだ」「大切な贈り物はいつも高島屋だった」…そんな温かい思い出がたくさん詰まった場所がなくなるのは、本当に寂しいことですよね。この記事では、そんな皆さまの気持ちに寄り添いながら、閉店に関する情報を一つひとつ丁寧に解説していきます。
この記事の目的は、単に「いつ閉店するのか」「なぜ閉店するのか」という事実を伝えるだけではありません。閉店の背景にある地域の変化や、百貨店業界全体の大きな流れ、そして最も気になる「閉店した後、あの場所はどうなるのか?」という未来の話まで、どこよりも詳しく、そして分かりやすくお伝えすることです。
最後まで読んでいただければ、この出来事の全体像がすっきりと理解でき、地域のこれからを考えるきっかけになるはずです。
【ひと目でわかる】髙島屋 洛西店・堺店 閉店の概要


読者の方が最も早く知りたいであろう顕在ニーズ(いつ、どこで、なぜ、どうなる)に即座に応えるため、まずは二つの店舗の閉店計画の要点をまとめた比較表をご覧ください。これにより、記事の冒頭で全体像を掴んでいただき、詳細な解説へと読み進めていただければと思います。
| 項目 | 髙島屋 洛西店 | 髙島屋 堺店 |
| 所在地 | 京都市西京区大原野東境谷町2-5-5 | 堺市堺区三国ヶ丘御幸通59 |
| 開店日 | 1982年4月16日 | 1964年10月 |
| 閉店予定日 | 2026年8月3日 (月) | 2026年1月7日 (水) |
| 営業期間 | 約44年 | 約61年 |
| 主な閉店理由 | 売上減少、建物の老朽化に伴う多額の設備投資の回収困難 | 継続的な営業赤字、黒字化の目途が立たない |
| 跡地の予定 | シニア向け分譲マンション及び商業施設の候補地 | 新ショッピングセンター「HiViE(ヒビエ)堺東」 |
| 閉店後の高島屋 | 隣接施設にサテライトショップ出店予定 (2026年9月〜) | 百貨店としては完全撤退 |
なぜ?髙島屋「洛西店」閉店の背景にある”街の変化”
髙島屋洛西店の閉店は、単なる一店舗の業績不振という言葉だけでは片付けられない、深い背景を持っています。それは、お店が生まれた「洛西ニュータウン」という街そのものの歴史と、40年以上の歳月をかけた変化と深く結びついているのです。
高島屋が公式に発表した閉店理由は、売上の減少、建物の老朽化、そして今後の黒字化が見込めないことでした 。特に、1982年の開店から40年以上が経過し、建物の維持・更新に多額の設備投資が必要な状況にありました 。
しかし、現在の売上規模や今後の消費環境を考えると、その莫大な投資を回収できる見込みが立たない、というのが閉店を決断した大きな理由です [ライバル記事]。
この決断の背景を理解するためには、洛西ニュータウンという街の成り立ちにまで遡る必要があります。
洛西店は1982年4月、京都市が進める巨大住宅地開発の中核施設として開業しました 。当時、この街は未来の理想的な郊外住宅地として大きな期待を背負っていましたが、計画当初にうたわれていた地下鉄東西線の延伸は、バブル崩壊などの影響で現在に至るまで実現していません 。
結果として、洛西ニュータウンは「鉄道のないエリア」となり、そこに立地する髙島屋洛西店は、全国的にも珍しい存在となりました。だからこそ、地域住民にとっては単なる百貨店ではなく、日々の生活を支える大黒柱のような、特別な存在だったのです 。
しかし、街が誕生してから40年以上の時が流れ、その姿は大きく変わりました。京都市の統計データによると、洛西ニュータウンでは近年、住民の高齢化が顕著に進行しています 。
特に60代から69歳の人口割合が京都市全体と比較して高い一方で、百貨店の主な顧客層となる20代から40代の働き盛り世代の割合は低い状況です 。さらに、人口そのものも平成7年(1995年)から平成22年(2010年)の間に23%も減少しており、街の活気を支える若い世代やファミリー層が減ってしまったのです 。
このような人口動態の変化は、百貨店の経営に直接的な影響を与えます。平日昼間の人通りはまばらになり 、売上はピーク時の半分程度にまで落ち込んでいたという声も聞かれます 。
かつてニュータウンの発展を支えた百貨店というビジネスモデルが、街と共に歳を重ね、現在の地域のライフスタイルや人口構成と少しずつ合わなくなってきていたのです。
髙島屋洛西店の閉店は、一つの企業の経営判断であると同時に、日本の多くの郊外ニュータウンが直面する「街の成熟と変化」という大きな課題を象徴する出来事と言えるでしょう。
堺の”顔”が…髙島屋「堺店」閉店と中心市街地の課題
堺東駅の”顔”として約60年間、地域のシンボルであり続けた髙島屋堺店の閉店は、多くの市民にとって衝撃的なニュースでした。この出来事は、単に一つの店舗がなくなるというだけでなく、堺市が長年取り組んできた「中心市街地の活性化」という大きなテーマに、改めて厳しい現実を突きつけるものとなりました。
堺店の閉店理由は、洛西店よりもさらに直接的な経営問題にあります。公式発表によると、2020年度に営業赤字を計上して以降、赤字基調が継続していました 。様々な営業努力を重ねたものの、黒字化の目途が立たないことから、建物の賃貸借契約が満了するタイミングに合わせて営業を終了するという、苦渋の決断に至ったのです 。
1964年、前回の東京オリンピックが開催された年に開業した堺店は、まさに堺市の発展と共に歩んできました 。南海高野線堺東駅に直結するという抜群の立地を誇り、地域のランドマークとして多くの人々の暮らしに寄り添ってきました 。
閉店のニュースに対し、地元の方からは「とても寂しい」「びっくりした」といった驚きの声と共に、「ここで初めて洗濯機を買った」「子どもの頃、屋上の遊具でよく遊んだ」といった、親子三代にわたる温かい思い出を惜しむ声が数多く寄せられています 。
この閉店が特に重く受け止められるのは、堺市がまさにこの堺東駅周辺エリアを「中心市街地」と位置づけ、官民一体となって活性化に取り組んでいる最中の出来事だからです。市は「堺市中心市街地活性化基本計画」を策定し、再開発事業や市民交流広場の整備、商店街の振興など、街に賑わいを取り戻すための様々な施策を推進してきました 。
これらの努力によって、一時は空き店舗率が目標値を達成するなど、活性化の兆しが見られた時期もありました 。しかし、新型コロナウイルス感染症の拡大が大きな打撃となり、再び空き店舗率が悪化するなど、中心市街地の商業環境は依然として厳しい課題を抱えています 。
このような状況の中で、地域の商業の”核”であり、街の”顔”でもあった百貨店が撤退するという事実は、市の活性化計画にとって大きな痛手です。
これは、インフラ整備や公共空間の創出といったハード面の施策だけでは、民間企業の厳しい経営環境という大きな流れを変えることがいかに難しいかを示しています。髙島屋堺店の閉店は、日本の多くの地方都市が抱える中心市街地活性化の難しさを浮き彫りにした事例とも言えるでしょう。
閉店後、どうなるの?跡地活用の計画と私たちの暮らし
地域の方々にとって最も気になるのは、「あの思い出の場所が、これからどう変わるのか」ということではないでしょうか。幸いなことに、髙島屋洛西店・堺店の両店舗ともに、すでに跡地活用の具体的な計画が発表されています。そこから見えてくるのは、それぞれの地域の特性や課題に合わせた、全く異なる未来像です。
洛西の未来:地域のニーズに応える「シニア向け分譲マンション」と「サテライトショップ」
洛西店の跡地活用は、地域の人口動態の変化に正面から向き合った計画となっています。閉店後の建物と土地は、近畿エリアを中心にシニア向けの分譲マンションを展開する事業者に売却されることが決定しました 。
今後は、分譲マンションと商業施設を組み合わせた形での再開発が進む予定です 。これは、高齢化が進む洛西ニュータウンの現状に寄り添い、シニア世代が安心して快適に暮らせる住環境を提供するという、非常に的を射た計画と言えます。
近畿圏では、サンヨーホームズの「サンミット」シリーズや、ハイネスコーポレーションの「中楽坊」シリーズなどがシニア向け分譲マンションとして知られています 。
そして、百貨店が完全になくなるわけではない、という点も地域住民にとっては朗報です。
髙島屋は、2026年9月から、隣接する商業施設「ラクセーヌ」内の一区画に「サテライトショップ」を出店することを計画しています 。これにより、これまで通り贈答品を選んだり、髙島屋がセレクトした人気商品を購入したりできる窓口が地域に残されることになります。
過去の髙島屋のサテライトショップの例を見ると、化粧品、ファッション雑貨、婦人服、ライフスタイル雑貨などが扱われており、規模は小さくとも百貨店ならではの品揃えが期待されます 。これは、長年の顧客との繋がりを大切にし、地域のニーズに応え続けようとする髙島屋の姿勢の表れです。
堺の未来:日常に寄り添う新しい「ショッピングセンター HiViE(ヒビエ)堺東」へ
一方、堺店の跡地は、駅直結という立地のポテンシャルを最大限に活かす形で生まれ変わります。建物を所有する南海電鉄は、髙島屋の営業終了後に大規模なリニューアル工事を行い、新たなショッピングセンター「HiViE(ヒビエ)堺東」を開業すると発表しました 。
そのコンセプトは、「より良い毎日に“Direct SC”」。これは、特別な日のためだけでなく、駅を利用する人々の通勤・通学といった日常のライフスタイルに直結する施設を目指す、という思いが込められています 。
これまでの百貨店とは異なり、スーパーマーケットや食物販、アパレル、雑貨店、飲食店など、毎日の暮らしに彩りと利便性をもたらすテナント構成が検討されています 。特別なハレの日の消費の場から、便利なケの日の暮らしの拠点へ。時代のニーズに合わせた大きな転換です。
なお、髙島屋内に入っていたユニクロやセリアといった一部のテナントや、南海堺東ビルの他のテナントは、基本的に営業を継続する予定であり、駅ビルの利便性が完全に損なわれるわけではない点も安心材料です 。
洛西と堺、二つの跡地活用計画は非常に対照的です。洛西は「地域の高齢化への適応」、堺は「駅前立地の再価値化」。それぞれの街が抱える課題に対し、市場原理に基づいた明確な答えが出された形であり、今後の街の姿を占う上で非常に興味深い事例となっています。
これは高島屋だけの問題じゃない?百貨店業界の大きなうねり
髙島屋の洛西店と堺店の閉店ニュースは、地域に大きな衝撃を与えましたが、これは決して髙島屋一社だけの問題ではありません。実は、この出来事は氷山の一角であり、今、日本の百貨店業界、特に地方や郊外に立地する店舗は、時代の大きな変化の波に直面しているのです。
百貨店が苦戦している背景には、複合的な要因がありますが、大きく分けると二つの流れが挙げられます。一つは、私たちの買い物の仕方を根本から変えた「インターネット通販(EC)の拡大」。もう一つは、将来への不安感などからくる「消費環境の不透明さ」です。
この10年ほどの間に、他の大手百貨店グループも、地方店の閉鎖や事業規模の縮小を次々と進めてきました。
例えば、セブン&アイ・ホールディングス傘下のそごう・西武は、2020年から2021年にかけて西武大津店(滋賀県)、そごう徳島店(徳島県)、そごう西神店(兵庫県)など5店舗の閉鎖を決定しました 。
三越伊勢丹ホールディングスも同様に、伊勢丹相模原店(神奈川県)や新潟三越(新潟県)など、多くの地方・郊外店の営業を終了させています 。髙島屋の今回の決定は、決して特別なことではなく、業界全体を覆うこの大きな構造変化の中に位置づけられるのです。
この構造変化の最大の要因は、Eコマースの急成長です。経済産業省の調査によると、衣料品や生活雑貨などを含む物販系分野のBtoC-EC(消費者向け電子商取引)の市場規模は年々拡大を続けています 。
スマートフォン一つで、いつでもどこでも欲しいものが手に入る時代になり、かつて百貨店が独占していた「豊富な品揃え」という価値は、オンラインの世界に取って代わられつつあります。
百貨店各社もオンラインストアの強化に努めていますが、そのEC化率(総売上高に占めるEC売上高の割合)は、髙島屋で4.2%など、まだ一桁台にとどまっているのが現状です 。
リアル店舗に目を向けても、状況は厳しいものがあります。日本百貨店協会の月次データを見ると、全国の百貨店の売上高は、インバウンド(訪日外国人)需要に支えられる都心店と、客足の減少に苦しむ地方店との格差が鮮明になっています 。
かつて百貨店が担っていた「特別な商品」「贈答品」「質の高い接客」「地域の催事場」といった様々な機能が、Eコマース、専門店、ショッピングモール、イベントスペースといった、より専門性の高い業態に一つひとつ切り分けられ、奪われていきました。
地方や郊外において、これら全ての機能を一つの巨大な建物で維持し続けるビジネスモデルが、限界に達しているのです。
【地元の方向け】気になる疑問にお答えします
閉店のニュースに接し、長年利用されてきた地域の方々にとっては、様々な疑問や不安が浮かんでいることと思います。ここでは、そうした個人的で実用的な疑問にQ&A形式でお答えします。
Q1: 持っている高島屋の商品券やポイントはどうなるの?
A: ご安心ください。髙島屋の商品券(タカシマヤギフトカード、百貨店共通商品券など)や、「タカシマヤポイントカード」に貯まったポイントは、全国の髙島屋各店で引き続きご利用いただけます。
洛西店をご利用だった方は、京都市内の京都店や大阪店で、堺店をご利用だった方は、同じく大阪店や泉北店などで、これまで通りお買い物ができます。有効期限のない商品券はもちろん、ポイントも有効期限内であれば失効することはありません。ご不明な点は、最寄りの髙島屋の窓口にお問い合わせください。
Q2: お中元やお歳暮など、贈り物はこれからどこで買えばいい?
A: これまで贈答品選びに髙島屋を利用されていた方にとっては、大きな問題ですよね。洛西地区にお住まいの方は、2026年9月から隣接する商業施設「ラクセーヌ」内にできる「サテライトショップ」が新しい窓口になります 。
小規模ながらも、ギフトの相談や申し込みができるようになると期待されます。また、両地域の方にとって便利なのが、髙島屋のオンラインストアです。品揃えも豊富で、ご自宅からゆっくりと商品を選んで注文できるため、大変便利です。もちろん、少し足を延ばして京都店や大阪店、泉北店といった近隣の大型店舗を訪れ、実物を見ながら選ぶという楽しみ方もこれまで通り可能です。
Q3: たくさんの思い出が詰まった場所がなくなるのが、ただただ寂しいです。
A: そのお気持ち、とてもよく分かります。SNSなどを見ても、「家族で食事したレストランの味が忘れられない」「初めての化粧品をカウンターで選んでもらった」「屋上のゲームコーナーが大好きだった」など、多くの方がそれぞれの思い出を語り、閉店を惜しんでいます 。
洛西店は約44年、堺店は約61年という長い間、ただの建物ではなく、街の景色の一部であり、人々の人生の節目に寄り添ってきた場所です。その記憶は、お店がなくなったとしても、利用した一人ひとりの心の中に、温かい光として残り続けるのではないでしょうか。この記事が、皆さまのそんな大切な思い出を振り返る一助となれば幸いです。
Q4: 地域の”顔”がなくなることで、街の価値やイメージは下がりませんか?
A: 大切なご心配だと思います。長年親しまれてきた百貨店というシンボルがなくなることは、一時的に地域のイメージに影響を与えるかもしれません。
しかし、最も重要なのは「その場所がどう生まれ変わるか」です。
洛西では、地域の人口構成に合わせた新しい住まいと商業の形が生まれます。堺では、駅前の利便性を活かした、日常に寄り添う新しい賑わいの拠点が計画されています。
これらの新しい施設が地域にしっかりと根付き、新たな”顔”として住民に愛される存在となることで、街の価値を維持し、あるいはこれまでとは違った形で向上させていくことが期待されています。変化は寂しさを伴いますが、新しい未来への第一歩でもあるのです。
結論:高島屋「洛西店」「堺店」閉店へ
髙島屋の洛西店と堺店の閉店は、長年利用してきた地域の方々にとって、言葉に尽くしがたい寂しさを伴うニュースです。しかし、これは単なる「終わりの物語」ではありません。それは、人口構成の変化、消費行動の変化、そしてEコマースの台頭という、日本全体が直面する大きな時代のうねりの中で起きた、ある種の必然的な出来事なのです。
本稿で詳述したように、洛西店はニュータウンの成熟と共にその役割を一つの区切りとし、堺店は中心市街地の再編という大きな流れの中で新たな一歩を踏み出すことになりました。そして、それぞれの跡地には、ただ空き地になるのではなく、地域の未来を見据えた新しい計画がすでに動き出しています。洛西はシニア世代が安心して暮らせる街へ、そして堺は毎日の生活がより便利で楽しくなる駅前へと、それぞれの形で進化を遂げようとしています。
長い間、私たちの暮らしに彩りと安心感を与えてくれた二つの髙島屋への感謝の気持ちと共に、これから始まる洛西と堺の新しい章に、静かに、そして前向きに注目していきたいと思います。この街で暮らす皆さまの毎日が、形は変わっても、これからも豊かであることを心から願っています。