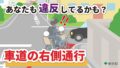2024年から2025年にかけて東急バスが横浜市内で実施する二段階の運賃改定は、単なる物価上昇への対応ではない。深刻化する乗務員不足、高騰し続ける運行コスト、そしてコロナ禍以降に定着した新たな生活様式という、バス業界全体が直面する構造的危機に立ち向かうための、包括的な経営戦略である。本稿では、この戦略的な価格再編が、利用者の負担にどう影響し、キャッシュレス化をいかに推進するのかを解き明かす。さらに、横浜の交通市場における競争環境の変化を分析し、地域交通ネットワークの持続可能性を確保するための企業の決断の裏側を徹底的に掘り下げる。
新たな経営環境に対応する二段階の戦略的運賃再編

横浜市内の東急バスの運賃は、近年二度にわたる改定が実施、または予定されている。一度目は2024年3月24日に実施され、二度目は2025年10月1日に実施された。これらの運賃改定は、単なる物価上昇に応じた値上げではなく、バス業界が直面する構造的な課題に対応するための、熟慮された二段階の戦略的再編と位置づけられる。
本稿では、これら二つの運賃改定の詳細を深く掘り下げ、その背景にある経営戦略、利用者への具体的な影響、そして横浜地域の交通市場における競争環境の変化について、網羅的かつ多角的に分析する。2024年の改定が、長年の運賃体系の歪みを是正し、来るべき本格的な値上げへの布石を打つ「地ならし」であったのに対し、2025年の改定は、決済方法による価格差を導入することで利用者の行動変容を促し、事業の効率化を加速させる「本丸」の施策である。
これらの動きは、深刻化する乗務員不足、継続的な運行コストの上昇、そしてコロナ禍以降定着した新たな生活様式という、公共交通機関が共通して抱える三重苦に対する東急バスの回答である。本分析を通じて、一連の運賃改定が、単なる利用者の負担増にとどまらず、地域交通ネットワークの持続可能性を確保するための不可欠な経営判断であったことを明らかにする。
東急バス運賃改定の概要(2024年・2025年)
| 項目 | 改定前(~2024年3月23日) | 2024年3月24日改定 | 2025年10月1日改定(予定) |
| 大人運賃(IC) | 220円 | 230円 | 240円 |
| 大人運賃(現金) | 220円 | 230円 | 250円 |
| 小児運賃(IC) | 110円 | 115円 | 120円 |
| 小児運賃(現金) | 110円 | 115円 | 130円 |
| 改定の主な特徴 | IC・現金同額 | 全線均一運賃の10円引き上げ | ICカードと現金の運賃差を導入 |
注:小児運賃は、2024年改定時にICカード利用時の端数処理により5円の差が生じたが、基本的な改定方針は大人運賃に準ずる。2025年改定ではIC/現金の価格差が明確に設定される 。 東急バス
2024年の運賃改定:運賃体系の統一と基盤的値上げ
2024年3月24日、東急バスは横浜市内、東京都内、川崎市内の均一運賃区間において、大人普通運賃を従来の220円から230円へと一律で10円引き上げた 。この改定は、ICカード、現金ともに同額であり、一見すると小幅な値上げに過ぎないように見えるが、その背景には二つの重要な戦略的意図が存在した。
歴史的背景と経営課題の是正
第一に、この改定は、消費税率の変更に伴う調整を除けば、東京都内・横浜市内においては1997年以来、実に27年ぶりとなる本格的な運賃引き上げであった 。この事実は、東急バスが長期間にわたり運賃を据え置くことで利用者の負担を抑制してきた一方で、その間に蓄積されたコスト増が事業経営を圧迫し続けていたことを示唆している。
第二に、より重要な戦略目的は、長年の経営課題であった川崎市内との運賃格差の解消である。歴史的に川崎市内の運賃は、東京都内・横浜市内よりも10円安く設定されており、この価格差が収益の不均衡を生み、経営の非効率性を招いていた 。2024年の改定では、先行して220円に値上げされていた川崎市内運賃を、他地区と同じ230円に引き上げることで、全営業エリアにおける運賃体系を統一した。これにより、サービス水準の均質化を図るとともに、収益構造の安定化を実現したのである。
規制当局への周到な布石
この2024年改定において最も注目すべき点は、単に実施運賃を230円に引き上げただけでなく、規制当局である国土交通省に対し、東京都内・横浜市内の上限運賃(認可上限運賃)を250円とする認可申請を行い、承認を得ていたことである 。
この一連の動きは、極めて周到な規制戦略であったことが見て取れる。上限運賃とは、事業者が収受できる運賃の上限額であり、一度認可を得れば、その範囲内での運賃変更は、比較的簡易な「実施運賃の変更届出」で済む。つまり、東急バスは2024年の段階で、将来的な250円までの値上げの「権利」を法的に確保していたのである。
この手続きを踏んだことで、翌2025年に計画されていた本格的な値上げ(ICカード240円、現金250円)の際には、再び大規模な認可申請プロセスを経る必要がなくなった。これにより、規制対応にかかる時間と労力を大幅に削減し、経営計画に沿った迅速な運賃改定を可能にした。2024年の10円の値上げは、利用者にとっては直接的な負担増であったが、経営戦略上は、歴史的な価格体系の歪みを是正すると同時に、次なる一手への道筋を確実にするための、極めて重要な布石であったと言える。
2025年の運賃改定:戦略的な価格多様化とキャッシュレス化の推進
2024年の基盤整備を経て、東急バスは2025年10月1日に、より踏み込んだ第二段階の運賃改定を実施する。この改定の核心は、単なる値上げにとどまらず、決済方法によって運賃に明確な差を設ける「価格の多様化」にある 。
新運賃体系の詳細
2025年10月1日始発より、横浜市内を含む東急バスの均一運賃区間における普通運賃は、以下のように変更される。
新運賃体系(2025年10月1日実施予定)
| 対象 | 決済方法 | 改定前運賃(~2025年9月30日) | 新運賃(2025年10月1日~) | 差額 |
| 大人 | ICカード | 230円 | 240円 | +10円 |
| 現金 | 230円 | 250円 | +20円 | |
| 小児 | ICカード | 115円 | 120円 | +5円 |
| 現金 | 115円 | 130円 | +15円 |
出典: 東急バス
この新体系では、ICカード利用時の運賃が240円であるのに対し、現金での支払いは10円高い250円に設定される。この価格差は、バス事業の運営効率を抜本的に改善するための強力なインセンティブとして機能することが期待されている。
ICカード・現金運賃差の再導入が持つ戦略的意味
2019年の消費税率10%への引き上げの際、多くのバス事業者は計算の簡素化を理由に、ICカードと現金の運賃を同額に統一した経緯がある 。しかし、今回の東急バスの決定は、その流れに逆行し、意図的に価格差を再導入するものである。この背景には、単なる過去への回帰ではなく、将来を見据えた明確な経営戦略が存在する。
バス事業において、現金での運賃収受は、目に見えない多くのコストを発生させる。
- 乗降時間の増大:乗客が現金や両替機を操作する時間は、バス停での停車時間を長引かせ、路線全体の定時運行を阻害する大きな要因となる。
- 現金管理コスト:営業所での現金の回収、計数、保管、そして金融機関への入金といった一連の作業には、人件費やセキュリティ対策費など、多大な管理コストがかかる。
- 乗務員の負担:運転と安全確認に加え、運賃収受や両替対応は乗務員にとって大きな負担であり、特に人材不足が深刻化する中では無視できない問題である。
ICカード利用を促進することは、これらの課題を同時に解決する有効な手段である。乗降がスムーズになれば定時性が向上し、現金管理コストが削減され、乗務員は運転業務に集中できる。今回設定された10円の価格差は、利用者に対してICカード利用の経済的メリットを明確に提示し、キャッシュレス決済への移行を強力に促すための「価格シグナル」である。これは、労働生産性の向上が急務であるバス業界において、事業の持続可能性を高めるための極めて合理的な経営判断と言える。
この運賃改定に合わせて、「東急バス一日乗車券」や「東急線・東急バス 一日乗り放題パス」といった企画乗車券の価格も引き上げられ、運賃体系の全体的な見直しであることが示されている 。
改定を駆動する力:業界全体を覆う構造的危機
東急バスが二段階にわたる大幅な運賃改定に踏み切らざるを得なかった背景には、個社の経営努力だけでは吸収しきれない、バス業界全体が直面する深刻な構造的危機が存在する。
人的資本の危機:深刻な乗務員不足と「2024年問題」
最大の要因は、業界全体を揺るがす深刻な乗務員不足である 。バスの運転は、高い専門性と責任を要求される一方で、労働条件の厳しさから若年層の入職者が伸び悩み、既存乗務員の高齢化が進行している。この問題に拍車をかけたのが、いわゆる「2024年問題」である。
2024年4月から施行された「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」の改正により、バス運転者の時間外労働の上限が厳しく規制されることになった 。これにより、従来は一部の乗務員の長時間労働によって維持されてきた路線網や運行便数を確保するためには、より多くの人員が必要となった。人材確保のためには、賃金の引き上げや福利厚生の充実といった労働条件の改善が不可欠であり、これが人件費の大幅な増加に直結している。運賃改定によって得られる増収分は、この人的資本への投資に充当され、路線の維持と安全運行の確保という、事業の根幹を支えるために不可欠な原資となる。
止まらない運行コストの上昇
人件費に加え、事業運営に関わるあらゆるコストが上昇を続けている。燃料費の高騰は言うまでもなく、安全性能が向上した新型車両の導入費用、バス停や営業所といった設備の維持・更新費用も年々増加している 。さらに、社会的な要請である脱炭素化への対応として、従来のディーゼル車よりも高価なEVバス(電気バス)の導入も進めなければならず、大規模な設備投資が継続的に必要となる 。これらのコスト増は、従来の運賃収入だけでは到底賄いきれないレベルに達している。
コロナ禍以降の新たな現実
新型コロナウイルス感染症の拡大は、人々の移動パターンを恒久的に変化させた。テレワークやハイブリッドワークの普及により、かつてバス事業の収益の柱であった通勤定期利用者が大幅に減少し、その需要はコロナ禍以前の水準には回復しないとの見方が支配的である 。利用者が減少する一方で、地域住民の移動手段を確保するという社会的責務から、赤字路線であっても安易に廃止することはできない。収入が減少する中で、広範な路線網を維持し続けなければならないというジレンマが、バス事業者の経営を一層困難にしている。
これらの複合的な要因が、東急バスを含む多くのバス事業者に対し、サービスの維持と事業の継続を可能にするための、痛みを伴う運賃改定という決断を迫っているのである。
利用者への影響と企業の社会的配慮
運賃改定は、企業の経営戦略であると同時に、日々の移動をバスに頼る利用者の家計に直接的な影響を及ぼす。東急バスは、財務基盤の強化という経営目標と、公共交通機関としての社会的責任との間で、慎重なバランスを取ろうとしていることがうかがえる。
通勤利用者への影響
今回の二度にわたる改定で、最も大きな影響を受けるのは、日常的にバスを利用する通勤者である。特に、通勤定期券の価格は段階的に引き上げられる。
大人通勤定期券の価格推移(改定前~2025年改定後)
| 期間 | 改定前(~2024年3月23日) | 2024年3月24日改定後 | 2025年10月1日改定後(予定) | 総上昇額 |
| 1ヶ月 | 9,850円 | 10,290円 | 10,800円 | +950円 |
| 3ヶ月 | 28,070円 | 29,330円 | 30,780円 | +2,710円 |
| 6ヶ月 | 53,190円 | 55,570円 | 58,320円 | +5,130円 |
出典: 東急バス
表が示すように、2年足らずの間に6ヶ月定期券の価格は5,000円以上上昇する計算となる。この負担増に対し、利用者が取りうる自衛策は明確である。
- ICカードの徹底利用:2025年10月以降、1回の乗車で10円の差が生じるため、SuicaやPASMOといった交通系ICカードの利用が経済合理性の観点から必須となる 。
- 定期券の早期購入:2025年10月1日の改定前に購入した定期券は、有効期間が10月1日以降にかかる場合でも、旧価格のまま期間満了まで使用できる 。したがって、特に3ヶ月や6ヶ月といった長期の定期券を更新する予定のある利用者は、9月中に購入することで、差額分の支出を抑えることが可能である。
「社会的契約」としての通学定期運賃の据え置き
一方で、東急バスが一貫して示している配慮が、通学定期券の運賃を据え置くという決定である。2024年、2025年の両方の改定において、同社は「家計への負担に配慮し」という理由を明確に掲げ、通学定期券を値上げの対象から外している 。
この判断は、単なる温情主義ではなく、高度な戦略的意図を含むものと分析できる。 まず、この措置は顧客を明確にセグメント化し、経済的に支払い能力が高いと見なされる社会人通勤者と、価格弾力性が高く社会的保護の必要性が大きい学生とを区別している。負担を社会人に集中させることで、値上げによる収益改善効果を確保しつつ、社会的な反発を最小限に抑えようという狙いがある。
次に、これは企業の社会的責任(CSR)を果たす姿勢を社会に示す、強力な広報戦略でもある。子育て支援や教育への貢献という大義名分は、運賃値上げというネガティブなニュースに対する「緩衝材」として機能する。これにより、東急バスは運賃改定を、単なる利益追求の動きではなく、社会全体の利益(=公共交通の維持)のためにやむを得ず行う措置であると位置づけ、利用者や社会からの理解を得やすくしている。この「社会的契約」とも言えるアプローチは、運賃改定を円滑に進める上で、極めて重要な役割を果たしている。
競争環境:横浜交通市場における価格構造の分化
東急バスの新たな運賃戦略は、同社単独の問題にとどまらず、横浜市内のバス市場全体の価格構造と競争環境に大きな変化をもたらす。
主要事業者との運賃比較
2025年10月以降、横浜市内を運行する主要なバス事業者の運賃は、明確に二つのグループに分化することになる。
横浜市内主要バス事業者の運賃比較(2025年10月1日時点)
| 事業者 | 大人IC運賃 | 大人現金運賃 |
| 東急バス | 240円 | 250円 |
| 横浜市営バス | 220円 | 220円 |
| 川崎鶴見臨港バス | 240円 | 240円 |
| 相鉄バス | 240円 | 240円 |
出典: 東急バス
この表から明らかなように、東急バス、臨港バス、相鉄バスといった民間事業者がIC運賃240円で横並びになる一方、公営の横浜市営バスは220円の運賃を維持する見込みである 。これにより、民間バスと市営バスの間には、1回の乗車あたりICカードで20円、現金では最大30円という、無視できない価格差が生まれることになる。
公営バスとの価格差拡大がもたらす影響
この価格構造の二極化は、横浜の公共交通ネットワークにいくつかの重要な変化を引き起こす可能性がある。
第一に、複数の事業者が競合する路線において、利用者の行動変容が起こる可能性がある。価格に敏感な利用者は、これまで以上に安価な横浜市営バスを選択するようになり、民間事業者の利用者が市営バスへと流出するかもしれない。これは、民間事業者の収益性に影響を与えるだけでなく、市営バスの特定路線における混雑を激化させる可能性もはらんでいる。
第二に、この状況は、公営交通のあり方そのものに問いを投げかける。横浜市営バスが運賃を据え置くことができるのは、その運営が市の税金によって支えられているからに他ならない。民間事業者がコスト増を運賃に転嫁せざるを得ない中で、市営バスが低価格を維持し続けることは、市民にとっては恩恵である一方、市の財政負担を増大させる要因にもなり得る。将来的には、市営バスも運賃改定の議論から逃れることはできず、その際には市民サービスと財政規律のバランスが問われることになるだろう。
このように、東急バスの運賃改定は、民間事業者が市場原理に基づいて持続可能性を追求する動きと、公営事業者が税金を背景にアクセシビリティを優先する動きとの間の差異を浮き彫りにした。これは、横浜のバス利用者が、居住地域や利用路線によって異なる価格帯のサービスを享受することになる、交通サービスの「市場分断」の始まりを示唆しているのかもしれない。
結論:公共交通の新たな時代を航行するために
横浜市内における東急バスの2024年から2025年にかけての二段階の運賃改定は、単なる値上げではなく、バス事業を取り巻く経営環境のパラダイムシフトに対応するための、包括的かつ戦略的な経営判断である。
本分析で明らかにしたように、この一連の改定は、深刻な乗務員不足、運行コストの高騰、そしてコロナ禍以降の需要構造の変化という、避けることのできない複数の危機に対する企業の適応策である。2024年の改定が運賃体系の統一と将来への布石という「守り」の側面を持つのに対し、2025年の改定はキャッシュレス化の推進による業務効率化という「攻め」の戦略へと転じている。
その過程で示された、通学定期運賃の据え置きという社会的配慮は、企業が財務的な持続可能性と、公共サービスとしての社会的責務との間でいかに繊細なバランスを取ろうとしているかを物語っている。一方で、この改定がもたらした民間事業者と公営事業者との間の価格差の拡大は、横浜の交通市場に新たな競争力学を生み出し、利用者と行政の双方に新たな選択と課題を突きつけている。
結論として、東急バスの運賃改定は、公共交通がもはや従来のビジネスモデルでは存続できない新たな時代に突入したことを象徴する出来事である。利用者は短期的な負担増に直面するが、それは地域社会の移動手段という不可欠なインフラを未来にわたって維持するために、社会全体で分かち合うべきコストの一部と捉える必要があるのかもしれない。今後、すべての交通事業者は、財務的な自立と公共的役割の両立という困難な課題を乗り越えていくための、さらなる革新と利用者の理解を求めていくことになるだろう。
【参考文献】