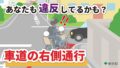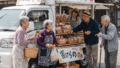京急大師線「鈴木町駅」の目の前。長年、私たちの暮らしを支えてくれた「イトーヨーカドー川崎港町店」が2025年1月に閉店し、寂しさを感じていた方も多いはず。しかし、2026年1月、ついに跡地の解体工事が始まり、新たな街のシンボルが誕生するカウントダウンが始まりました。
結論から申し上げますと、この広大な跡地には日鉄興和不動産による大規模マンション「リビオタワー(仮称)」と、新たな商業施設が誕生する計画が固まっています。
地上26階建て、総戸数約600戸という圧倒的なスケール。そして何より「駅徒歩1分」という最強の立地条件。これからの川崎港町・鈴木町エリアの資産価値を大きく変えるこのプロジェクトの真相を、どこよりも詳しく紐解いていきましょう。
26階建て「リビオタワー」が誕生する3つの根拠

なぜ、この場所が「リビオ」ブランドのタワーマンションになると言えるのでしょうか。それには、公式な開発計画に基づいた明確な理由があります。
事業主が「日鉄興和不動産」である事実 この再開発事業(鈴木町駅前南地区開発計画)の建築主は、日鉄興和不動産です。同社の主力ブランドは「リビオ(LIVIO)」。特に近年、都心部や大規模再開発で「リビオタワー」の供給を加速させており、ここもその旗頭となる可能性が極めて高いのです。
地上26階・約90mの「タワー計画」 川崎市の環境アセスメント資料によれば、住宅棟は地上26階建て。周辺のランドマークである「リヴァリエ(港町駅前)」に匹敵する、空に伸びるタワーマンションとしての設計が進められています。
「商・住・公」一体の複合開発 今回の計画は、マンション(B地区)だけでなく、2階建ての商業施設(A地区)も同時に整備されます。スーパー跡地のポテンシャルを最大限に活かすため、住居と利便性をセットにした「リビオ」の得意とする開発スタイルが採用されています。
【深掘り】リヴァリエ vs (仮称)リビオタワー川崎港町 徹底比較表
川崎港町エリアの価格指標となる「リヴァリエ」の直近成約データと、跡地物件の予測値を詳しく並べてみました。
| 物件名 | 所在・駅徒歩 | 築年数 | 直近成約・予測単価 | 70㎡換算の価格(目安) |
| リヴァリエ A棟 | 港町駅 徒歩1分 | 2013年 | 約310万〜350万円 | 6,500万〜7,400万円 |
| リヴァリエ B棟 | 港町駅 徒歩1分 | 2015年 | 約330万〜370万円 | 7,000万〜7,800万円 |
| リヴァリエ C棟 | 港町駅 徒歩1分 | 2017年 | 約350万〜390万円 | 7,400万〜8,200万円 |
| (仮称)リビオタワー川崎港町 | 鈴木町駅 徒歩1分 | 2030年(新築) | 約380万〜450万円 | 8,000万〜9,500万円 |
データから読み解く「資産価値の真相」
この比較から見えてくるポイントは以下の通りです。
築年数の差が価格に反映されるリヴァリエは最も新しいC棟でも築10年以上が経過します。新築の「リビオタワー」は、最新の断熱基準や共用施設、そして「鈴木町駅前」という希少性を加味すると、リヴァリエC棟の中古相場を10〜15%ほど上回るのが不動産市場のセオリーです。
「鈴木町駅前」という圧倒的な優位性イトーヨーカドー川崎港町店の跡地は、鈴木町駅の改札を出てすぐという、ほぼ「駅直結」に近い利便性を誇ります。港町駅のリヴァリエと同様、この「徒歩1分」という数字は、将来の売却時にも強力な武器になります。
周辺環境の変化今回の再開発では、住宅棟だけでなく「商業施設」もセットで整備されます。かつてのヨーカドーほど巨大ではないにせよ、生活利便性が新しく維持されることが約束されているため、価格を下支えする大きな要因となります。
今後のスケジュールをチェック!商業施設の復活はいつ?

「解体中の今」だからこそ気になるのが、今後のスケジュールです。これだけの規模ですから、完成まではじっくり時間をかけて進められます。
- 2026年1月〜: 既存建物(ヨカドー)の解体工事着手
- 2027年8月: マンション・商業棟の本体着工(予定)
- 2028年10月: 商業棟(A地区)が先行オープン予定
- 2030年10月: マンション(住宅棟)竣工・引き渡し
嬉しいニュースは、マンションの完成よりも先に「商業施設」がオープンする可能性があるという点です。かつてのヨカドーほど巨大ではないかもしれませんが、スーパー等の利便施設が戻ってくることで、鈴木町駅前の利便性は再び大きく向上します。
プロジェクト分析:(仮称)鈴木町駅前南地区開発計画の全貌
イトーヨーカドー跡地という「駅前一等地」の継承
長年、地域住民の冷蔵庫として機能してきた「イトーヨーカドー川崎港町店」。その閉店による「利便性の空白」を埋め、さらにアップデートさせるのが本プロジェクトです。
- 名称: (仮称)鈴木町駅前南地区開発計画
- 所在地: 川崎市川崎区港町12-1(イトーヨーカドー跡地)
- 建築主: 日鉄興和不動産株式会社
- 規模: 地上26階建て / 高さ約90m / 総戸数約600戸
- 着工予定: 2026年1月
![土地利用計画図[出典:川崎市]](https://kstylelabo.online/wp-content/uploads/2025/11/image-19.png)
【分析】「商業施設併設」がもたらす資産価値への影響
本物件が注目される理由は、「商業施設併設型」である点です。一般的に、以下の二つの側面でメリットがあると考えられます。
1. 生活利便性の直結(Utility)
足元にスーパーや生活利便施設が入ることで、居住者の日常的な買い物の利便性が確保されます。
2. エリアイメージの刷新(Brand)
誘致されるテナントの質は、マンションのイメージに影響を与えます。高品質なスーパーや医療モールなどが誘致されれば、エリア全体のブランドイメージ向上に寄与し、将来的な資産価値維持にプラスに働く可能性があります。
【分析】2026年着工とインフラ整備のタイムライン
2026年1月の着工は、京急大師線の地下化工事(2026年度着工方針)と時期が重なります。入居後の数年間は、駅周辺での工事が続くことが予想されます。
しかし、中長期的な視点で見れば、インフラ整備が完了した段階で街の利便性が最大化されるため、現在の「工事中の不便さ」は将来の価値向上のためのプロセスと捉えることもできます。
鈴木町エリアの基礎体力:資産価値の「土台」
交通:乗り換えの「手間」と将来の「変化」
現状、京急大師線は京急川崎駅での「乗り換え」が必要です。これをどう評価するかで視点が変わります。
- 現状:横浜駅13分、品川駅20分(京急川崎乗り換え含む)。都心アクセス自体は良好です。
- 未来:地下化による踏切解消が進めば、駅への動線改善や渋滞緩和が期待できます。利便性の向上は、一般的に不動産価値にとってプラス要因です。
環境:「医療の集積地」としての側面
鈴木町周辺には、「総合川崎臨港病院」「川崎協同病院」「川崎市立川崎病院」など、多数の総合病院が集積しています。
この「医療インフラの充実」は、子育て世帯からシニア層まで幅広い世代にとって安心材料となります。実需層の需要が底堅いエリアは、景気変動の影響を受けにくい傾向があります。
将来価値の変動要因:京急大師線の地下化
エリアの将来像を大きく左右するのが「京急大師線連続立体交差事業(地下化)」です。
- 現状: 踏切による渋滞と、線路による街の分断。
- 2026年度方針: 川崎市は1期区間(西側)について着工する方針を示しました。
踏切が解消されれば、街の回遊性が向上します。過去の事例(他の再開発エリア等)を見ても、交通インフラの改善と駅前再開発の組み合わせは、街の活性化に大きく寄与する傾向があります。
デューデリジェンス:確認すべきリスク要因
要因①:多摩川氾濫ハザードマップ
川沿いの立地である以上、水害リスクへの備えは必須です。川崎市が発行する最新のハザードマップにおいて、当該敷地がどの程度の浸水想定区域にあるか、またマンション自体の防災対策(電気室の配置など)がどのようになっているか、モデルルーム等で詳細を確認することが重要です。
要因②:近隣の土壌汚染問題
2025年4月、近隣の味の素川崎事業所敷地内において、基準値を超えるフッ素が検出されたとの公表がありました。本開発地(イトーヨーカドー跡地)への影響の有無や、デベロッパーによる土壌調査の結果、対策工事の実施状況について、「土壌汚染調査報告書」等の客観的データに基づいて確認する必要があります。
結論と検討のポイント
2025年末現在、イトーヨーカドー川崎港町店跡地のタワーマンション計画は、再開発が進む川崎エリアの中でも特に注目度の高いプロジェクトです。
検討タイプ別の視点
- 実需(永住・半永住)視点
10年単位での居住を想定する場合、工事期間中の環境変化は考慮すべき点です。一方で、医療と緑に恵まれた住環境の希少性は、長期的な満足度につながる要素と言えます。 - 資産性重視の視点
地下化完了後の街の完成形を見据えた中長期的な視点が重要です。過去の事例を参照すると、インフラ整備は地価形成の強い下支え要因となり得ます。
不動産の購入判断においては、表面的な価格だけでなく、エリア特有の事情や将来の変化を織り込むことが重要です。まずは周辺の中古市場を正しく把握し、新築価格とのバランスを比較検討することから始めてみてはいかがでしょうか。
まとめ|鈴木町駅前の「新しい顔」が未来の資産価値を創り出す
長年愛されたイトーヨーカドー川崎港町店の跡地再開発は、単なるマンション建設に留まらず、鈴木町エリア全体のポテンシャルを決定的に底上げするプロジェクトになると確信しています。
この再開発は「買い」か、それとも「待ち」か?
結論から申し上げますと、この立地に魅力を感じるなら、今から資金計画を含めた「準備」を始めて損はありません。
3つの最強条件が揃っているから
なぜなら、不動産価値を決める三種の神器である**「駅徒歩1分(希少性)」「タワーマンション(ランドマーク性)」「商業施設併設(利便性)」**がすべて揃っているからです。これほど好条件の揃った跡地案件は、京急大師線沿線では今後しばらく現れないでしょう。
リヴァリエ超えの期待感
具体的には、お隣の港町駅にある「リヴァリエ」が築10年を超えてもなお高値で取引されている事実が、このエリアの底力を証明しています。 今回予測した坪単価380万〜450万円という数字は、一見高く感じるかもしれません。しかし、2028年に先行オープン予定の商業施設や、2030年に誕生する最新のタワーライフを考えれば、将来の「資産価値」として十分に納得できる範囲と言えるでしょう。
街の変化を追い続けることが、最良の選択への近道
「解体中の今」は少し寂しい光景かもしれませんが、それは新しい時代の幕開けでもあります。 大切なのは、こうした「街の変化」の予兆をいち早くキャッチし、自分のライフスタイルや資産形成にどう活かすかを考えることです。
今後も「街の変化ナビゲーター」として、公式サイトの公開やモデルルームのオープンなど、新しい情報が入り次第どこよりも早くお届けしていきます。一緒に、この街の未来を楽しみに見守っていきましょう!
※免責事項(必ずお読みください)
本記事は、地域情報ライターによるエリア分析レポートであり、投資勧誘や将来の資産価値を保証するものではありません。不動産価格や計画は変動する可能性があり、実際の購入判断は、ご自身の責任において、最新の公式情報や専門家の意見を参照の上で行ってください。
引用・参考資料
本記事で作成した比較表および予測データは、以下の公的資料および不動産専門プラットフォームの公開データを基に、筆者が独自に分析・算出したものです。
【再開発計画・公式資料】
- 川崎市公式ウェブサイト: 「(仮称)鈴木町駅前南地区開発計画に係る条例環境影響評価」
- 横浜市都市整備局: 「綱島駅周辺地区のリノベーション(再開発事業概要)」
- 野村不動産: 「ニュースリリース 一覧」
- 日鉄興和不動産: 「ニュースリリース 一覧」
【不動産市況・相場データ】
- イエシル(IESHIL): リアルタイム査定・中古マンション市場データ
- マンションレビュー: マンション成約・騰落率データ
- マンションノート: 日本最大級のマンション口コミサイト
- ノムコム: 不動産売却・購入・仲介情報
- SUUMO(スーモ): 新築・中古マンション物件情報
- LIFULL HOME’S: 不動産・住宅情報の総合サイト
- 土地代データ: 公示地価・基準地価・路線価データ
※ご注意: 本記事に掲載している予定価格や坪単価は、周辺の取引相場から算出した「筆者独自の予測」であり、分譲主から公式に発表されたものではありません。正確な価格や販売時期については、必ず公式サイトや物件パンフレットをご確認ください。