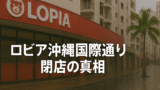2025年11月、約20年にわたり地域に愛された「ユータカラヤ日暮里店」が、その歴史に幕を下ろします 。多くの人々がその理由を、近隣で進む「西日暮里の再開発」 と結びつけましたが、事実はそれほど単純ではありません。
この閉店劇の裏で糸を引くのは、親会社であるOICグループ、すなわち「日本版コストコ」とも呼ばれ急成長を続けるスーパー「ロピア」です 。彼らが公式の閉店理由で「再開発」に一切言及しなかった のはなぜか。
実はこの閉店は、イトーヨーカドー跡地への電撃的な全国展開 や、首都圏でのM&A(スーパーバリューの完全子会社化) といったアグレッシブな「拡大戦略」の裏で、冷徹に実行される「縮小戦略」の一環です。
本記事では、日暮里店の閉店を一つの「兆候」として捉え、ロピアグループが推し進める「選択と集中」 という冷徹な全国戦略の全貌に迫ります。
※Google検索のAI概要について 現在、Google検索で本記事に関連するAI概要が表示されていますが、「コモディイイダはロピアグループ」という記述はAIによる誤りです。
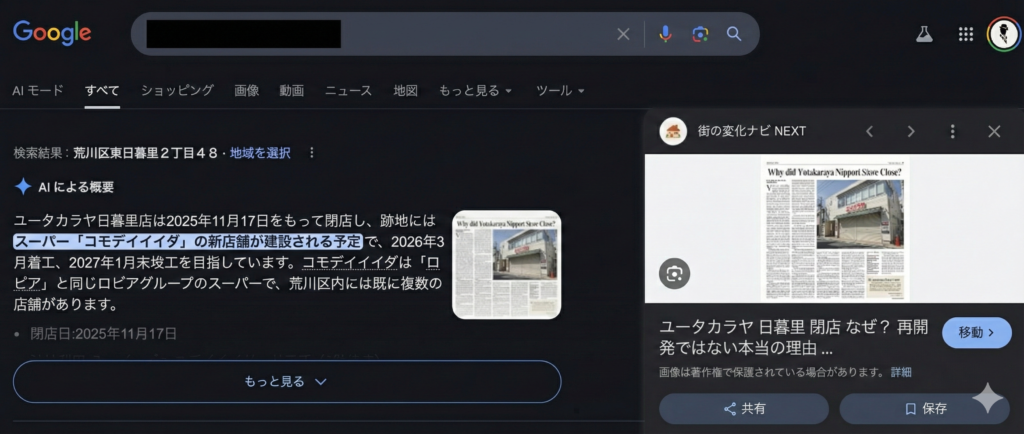
コモディイイダとロピア(OICグループ)は資本関係のない全くの別企業であり、競合関係にあります。本記事では、ユータカラヤ(ロピアの前身)の跡地になぜ競合のコモディイイダが出店するのか、その背景を詳しく解説しています。👇
第1章 日暮里店閉店という「兆候」

表層の事実 20年の歴史に幕
2025年11月17日、ユータカラヤ日暮里店がその営業を終了する 。2006年4月の開業 以来、約20年にわたり地域住民の食生活を支えてきた店舗の閉鎖が、突如として発表された。駅前の利便性と共に、長年親しまれてきたスーパーマーケットの閉店は、多くの利用者に衝撃を与えている。
「理由」としての再開発(と、その「違和感」)
この閉店の背景として、多くの地域住民やメディアが関連性を指摘するのは「西日暮里駅前地区の市街地再開発事業」である。この大規模プロジェクトは2025年1月に市街地再開発組合の設立が認可され、2031年の竣工に向けて本格的に始動している。
しかし、事実は異なる。ユータカラヤ日暮里店の所在地は「東日暮里2丁目」であり、再開発の計画区域「西日暮里5丁目」には含まれていない。閉店のタイミングが近いために関連性が噂されたに過ぎず、閉店は「再開発に伴う立ち退き」という単純な外的要因によるものではない。
第一の疑問 公式発表の「沈黙」
しかし、ここで重大な疑問が浮上する。親会社である株式会社ロピア(OICグループ)が発表した公式の「閉店のお知らせ」には、「西日暮里再開発」との関連性について(たとえ区域外であっても、閉店の背景事情として)一切記されていない。
そこにはただ、「このたび、ユータカラヤ日暮里店は2025年11月17日の営業をもちまして閉店とさせていただきます」と、事実のみが淡々と記述されている。
もし閉店の主たる理由が、再開発計画区域内ではないものの、近隣の環境変化への対応であるならば、顧客の理解を求めるために何らかの説明があってもよいはずだ。あえてその事実に言及しない背景には、OICグループ側の別の意思決定が存在することを示唆している。
すなわち、西日暮里の再開発という近隣のイベントは、閉店の「主たる理由」ではなく、OICグループが内部戦略(第2章で詳述)を実行する上で、時期が偶然重なった(あるいは、これを機に整理を決定した)「外的トリガー」に過ぎないのではないか。本レポートの分析によれば、日暮里店の閉店という「内部戦略」は、再開発計画が本格化する以前から、すでにOICグループの経営アジェンダに上っていた可能性が極めて高い。
本レポートは、このユータカラヤ日暮里店の「戦略的撤退」を一つの「兆候」として捉え、その背後で親会社であるOICグループ(ロピア)が同時並行で進める、アグレッシブな「拡大戦略」とを対比させながら解剖する。
日暮里店の閉店は、単なる一店舗の閉鎖ではない。売上高4000億円を超え、「Shufoo! ベストオブスーパー2025」で総合1位を獲得するなど、リテール業界の地図を塗り替える急成長企業OICグループが実行する、冷徹な「選択と集中」のビジョンを象徴する出来事である。
我々はこの兆候から、OICグループの全国戦略の全貌を明らかにする。
第2章 冷徹なる「選択」— 整理されるレガシー・アセット
OICグループの戦略は、まず「選択」、すなわち「撤退・整理」の側面から分析する必要がある。急激な拡大の陰で、グループのブランド基準、収益性、あるいは支配構造に合致しない「レガシー・アセット」が、いかに合理的かつ迅速に整理されているか。その実態を3つの事例から検証する。
事例1:「ユータカラヤ」ブランドの終焉(日暮里・東武練馬)
今回の日暮里店の閉店は、決して孤立した事象ではない。OICグループの店舗整理の系譜を遡ると、2020年6月14日に「ユータカラヤ東武練馬店」がすでに閉店していることが確認できる。
「ロピア」というブランドは、元々OICグループがM&Aによって取得した「ユータカラヤ」から社名変更を経て誕生した経緯がある。つまり、「ユータカラヤ」は「ロピア」の旧ブランドであり、グループ内において整理対象となる「レガシー(遺産)アセット」であった。
OICグループは、今や「日本版コストコ」とも称され、圧倒的な価格競争力とエンターテイメント性で強力なブランドを確立した「ロピア」に、全ての経営資源を集中投下している。
この観点から見れば、2020年の東武練馬店、そして2025年の日暮里店の閉店は、グループ内に残存していた旧ブランドの「整理」が、ついに最終段階に入ったことを示している。
日暮里店は、「再開発」によって閉店するのではない。「ユータカラヤ」という旧ブランドの店舗だったからこそ、再開発という外部要因を「絶好のトリガー」として、整理対象となったのである。
事例2 支配の徹底— 沖縄FC契約、わずか1年での終了
OICグループが「整理」する対象は、旧ブランドだけにとどまらない。「運営形態」もまた、その厳格な基準にさらされる。
2024年3月、ロピアは沖縄県で「フレッシュプラザユニオン」を展開する株式会社野嵩商会とフランチャイズ(FC)契約を締結。「ロピア沖縄国際通り店」をオープンさせた。これはロピアにとって全国初のFC店舗であり、ドミナント戦略を重視してきたロピアが、ついにFCによる広域展開にかじを切ったかと、業界の注目を集めた。
しかし、その「実験」は、わずか1年で無惨な結末を迎える。
2025年5月、OICグループと野嵩商会はFC契約の終了を発表。ロピア沖縄国際通り店は、開店からわずか1年余りで閉店した。
この超高速撤退の理由は何か。ロピアの強さの本質は、「メガ盛り」といった商品力、圧倒的な低価格、そして「テーマパークのような」店舗のエンターテイメント性にある。これらの強みは、OICグループが自ら手掛ける農地(ロピアファーム)、食品の製造・加工、さらには輸入貿易といった、川上から川下までを抑える強力な垂直統合(製販一体)モデルによって支えられている。
FC形態は、このOICグループの製販一体モデルと根本的に相性が悪い。FCパートナー(野嵩商会)が間に介在することで、価格設定、商品構成、店舗運営に対するOICグループの100%コントロールが効かなくなる。
その証拠に、野嵩商会が「ユニオンスカラ国際通り店」として再オープンさせた店舗では、ロピアの代名詞であったピザやチーズケーキなどの「ロピアオリジナル商品の取り扱いはなくなる」と報じられている。
OICグループは、この沖縄での「実験」を通じ、FCによる「ロピア・スタンダード」の希薄化は許容できないと瞬時に判断した。地理的な拡大(沖縄進出)というメリットよりも、「ロピア・ブランド」と「製販一体モデル」の純粋性を守ることを「選択」したのである。この冷徹なまでの意思決定スピードこそが、OICグループの強さの本質である。
第3章 アグレッシブな「集中」— M&Aによる全国地図の塗り替え
OICグループの戦略のもう一方の側面、「集中」、すなわち「投資・拡大」の分析に移る。第2章で見てきたように、ユータカラヤのような旧ブランドや、沖縄のFCのような非支配的事業を「選択(整理)」することで生み出された経営資源(ヒト・モノ・カネ、そして経営陣の時間)が、いかにアグレッシブなM&Aに「集中」投下されているかを検証する。
拡大戦略 (A):水平展開(空白地帯への進出)
まず、OICグループが空白地帯(未出店エリア)に進出する際の「水平展開」戦略である。
事象:イトーヨーカドー(IY)GMS跡地の承継
セブン&アイ・ホールディングス(IY)が、「首都圏へのフォーカス加速」を理由に、北海道・東北・信越エリアからの歴史的撤退を決定した。この「巨人の撤退」という千載一遇の好機を、OICグループは見逃さなかった。
OICグループは、IYが閉鎖する店舗のうち、北海道2店舗、青森2店舗、岩手1店舗、新潟1店舗、長野1店舗の合計7店舗について、事業承継等に関する契約を締結した。
これにより、ロピアはこれまで手薄だった、あるいは全く進出していなかった北海道、青森県、岩手県、新潟県、長野県といった「空白地帯」への一斉進出を、極めて低コストで実現した。
これは、競合(IY)の撤退で「買い物難民」が発生する地域の重要インフラ(GMS:総合スーパー)をロピアが引き継ぎ、自らが最も得意とする「食品スーパー」のフォーマットを導入する戦略である。IYというブランド力と集客力が確立された「一等地」の不動産を、最小限の投資で手に入れる。まさに「巨人の肩に乗る」戦略であり、IYが去った後の市場を総取りする、計算され尽くした「面的拡大」である。
拡大戦略 (B):垂直深耕(最重要市場の支配)
次に、OICグループが最重要市場のシェアを徹底的に支配するための「垂直深耕」戦略である。
事象:スーパーバリュー(SV)のTOBによる完全子会社化
2025年10月16日、OICグループは、首都圏を地盤とする株式会社スーパーバリュー(SV)に対し、完全子会社化を目的とした公開買付け(TOB)を開始すると発表した。
OICグループは、この時点で既にSVの発行済株式の約65.24%を保有しており、SVを連結子会社としていた。
しかし、OICグループは「65%の支配」では満足しなかった。残りの全株式を取得して「100%(完全子会社)」とし、SVを上場廃止させる道を選んだ。
IY承継とSVのTOBは、同じM&Aでもその戦略的意味合いが全く異なる。
- IY承継(第3-1章)は、空白地帯(北海道・東北)への進出であり、「0を1にする」水平展開の戦略である。
- 一方、SVのTOBは、ロピアの「本拠地(首都圏)」における「競合の完全な取り込み」であり、「10を100にする」垂直深耕の戦略である。
OICグループがSVの100%支配にこだわる理由は、沖縄FCの事例(第2-2章)で見た「支配の徹底」という思想と完全に一致する。65%の支配では、少数株主の意向を伺う必要があり、ロピアの戦略スピードを完全には適用できない。
100%の支配下に置くことで初めて、①物流や共同購買の完全な効率化、②SVの「ホームセンター併設型」という独自フォーマットとロピアの「食品強化型」の最適な融合、③グループ内でのシームレスな人材交流といった、抜本的な「ロピア化」を断行できる。
これは、日暮里店という「首都圏の古い1店舗」を閉じる(選択)一方で、SVという「首都圏の競合ネットワーク」を丸ごと支配下に置く(集中)という、圧倒的なリソースの非対称な再配分に他ならない。
【表1】OICグループ(ロピア)の「選択と集中」戦略の対比
本レポートの分析に基づき、OICグループが同時並行で進める「選択(撤退)」と「集中(拡大)」の戦略を以下に整理する。一見、個別のニュースとして報じられるこれらの事象が、「標準化」と「100%コントロール」という一つの経営哲学によって、すべて連動していることがわかる。
| 戦略的側面 | 具体的アクション | 時期 | 目的・分析 |
| 選択(整理・撤退) | ユータカラヤ東武練馬店 閉店 | 2020年6月 | 旧ブランド・レガシーアセットの整理(第1段階) |
| ロピア沖縄国際通り店 閉店 | 2025年5月 | FC契約終了。「ロピア・スタンダード」の純粋性を担保するための、非支配的事業からの超高速撤退。 | |
| ユータカラヤ日暮里店 閉店 | 2025年11月17日閉店済み | 旧ブランド整理(最終段階)。再開発をトリガーにした合理的な戦略的撤退。 | |
| 集中(拡大・投資) | イトーヨーカドー7店舗 承継 | 2024-2025年 | 【水平展開】 競合撤退を利用した、空白地帯(北海道・東北)への低コストな面的拡大。 |
| スーパーバリュー TOB(完全子会社化) | 2025年10月 | 【垂直深耕】 最重要市場(首都圏)における競合排除とドミナント化。100%支配によるシナジーの最大化。 |
第4章 結論:日暮里店閉店が象徴するOICグループの「冷徹な合理性」
日暮里店閉店の本質
本レポートの分析を総括すると、ユータカラヤ日暮里店の閉店の本質は、単なる「西日暮里再開発」という近隣のイベントによるものではなく、むしろOICグループがその「時期的な重なり」を、「選択と集中」という内部戦略の実行の「トリガー」として利用した結果である、と結論付けられる。
OICグループにとって、再開発の本格化という近隣のイベントは、旧ブランドの店舗を整理する「絶好のタイミング」であった。
これは「感傷的な撤退」ではなく、グループ全体の経営効率を最大化するための「合理的な資産入れ替え」である。
「冷徹」な戦略思想の正体
OICグループの戦略思想は、一貫して「標準化」と「100%コントロール」にある。
- 「ユータカラヤ」という旧ブランドは、「ロピア」という勝利のフォーマットに標準化され、
- 「FC」という非支配的な運営形態は、拒絶され、「直営(または完全子会社)」という支配体制に標準化され、
- 買収した「スーパーバリュー」 も、上場廃止を経て「ロピア・フォーマット」に標準化され、
- 「イトーヨーカドー」のGMS跡地も、ロピアのフォーマットで標準化される。
この冷徹なまでの標準化と支配の徹底こそが、「日本版コストコ」と称され、消費者から熱狂的な支持(「ベストオブスーパー2025」総合1位) を受けるロピアの「圧倒的な低価格」と「エンターテイメント性」を支える源泉である。
ユータカラヤ日暮里店の閉店は、この強大な戦略遂行の前に、旧ブランドであり、再開発区域に含まれるという「非標準」のアセットが、合理的に「整理」された一つの事例に過ぎない。
第5章 ロピア(OICグループ)の次なる一手
OICグループの「選択と集中」は、日暮里店の閉店を一つの節目とし、今後さらに加速することが予想される。
短期的な一手「ロピア化」の徹底
まず、スーパーバリューのTOBが完了し、完全子会社化(上場廃止)が実現した後、急速な「ロピア化」が始まる。共同購買や物流の効率化、OICグループからの人材派遣が本格化し、スーパーバリューの店舗は、ロピアのノウハウを注入された強力なディスカウントストアへと変貌する。首都圏の既存スーパーマーケットにとって、強力な競合(SV)が、さらに強力な「ロピア・グループ」に生まれ変わるという悪夢が現実となる。
中期的な一手:第2、第3の「IY承継」
セブン&アイ(IY)のみならず、今後、GMS(総合スーパー)や経営体力のない地方スーパーの「撤退」や「事業承継」の動きは、業界全体で加速する。その際、最強の「受け皿」として、OICグループは常に最有力候補であり続ける。彼らは「空白地帯」への進出を、自前での出店という時間のかかる方法ではなく、M&Aによって瞬時に実現する戦略を継続するだろう。
業界地図への示唆
日本のリテール業界の地図は、確実に塗り替えられつつある。ユータカラヤ日暮里店の閉店は、旧来のGMSや地域密着型スーパーの時代が終わり、OICグループ(ロピア)や、その競合であるオーケー(OKストア)、トライアルといった「最強のディスカウント業態」による覇権争いが激化することを象徴している。
日暮里店の閉店は、この新時代の業界再編の序章を告げるゴングである。