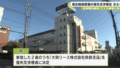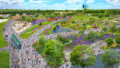AIによる概要にある閉店理由:土地所有者による土地開発の意向。この曖昧な回答について深堀りします。滋賀県大津市瀬田の玉野浦地区で、「瀬田 ヤマダ電機 跡地」や「ナフコ 瀬田 跡地」、「コナズ珈琲 瀬田 跡地」に関する検索が急増しています。
これらの店舗が相次いで閉店し、広大な敷地が更地になる中、「跡地に何ができるのか?」と多くの地域住民が注目しています。
本記事では、この一連の動きが単なる個別の閉店ではなく、平和堂とカインズによる大規模な複合商業施設の建設計画を伴う「玉野浦 土地開発」の一環であることを徹底解説。各店舗の閉店から新施設の全貌、そしてこの再開発が地域の未来に与える影響まで、あなたの疑問にすべてお答えします。
地域の名店の閉店が示す経済的指標

2025年8月17日をもって、ハワイアンパンケーキカフェ「コナズ珈琲大津店」が閉店、地域社会に少なからぬ驚きをもたらしました。2020年に滋賀県内初出店としてオープンして以来、多くの人々に親しまれてきたこの店舗は、単なる飲食店ではなく、地域における人気の集いの場としての役割を担っていました 。
公式に発表された閉店理由は「オーナー様の土地開発の意向を受けて」というものでした 。
この一見抽象的な表現は、多くの疑問を呼び起こします。本レポートの目的は、この「土地開発の意向」という言葉を法制度的、経済的、そして都市計画的観点から多角的に解き明かし、コナズ珈琲大津店の閉店が、大津市玉野浦地区で進行しつつある、より大きな都市変容の一端であることを明らかにすることにあります。
この閉店は、事業不振によるものではなく、店舗が立地する「土地」そのものの価値と将来性に関する所有者の戦略的判断が根本にあることを示唆しています。したがって、この出来事を個別の店舗の閉店として捉えるのではなく、都市の成長と再開発のダイナミクスの中で、土地という資産がどのように評価され、その利用方法が決定されていくのかを理解するための重要なケーススタディとして分析します。
本稿では、まず日本の都市計画法における「土地開発」の法的な定義と手続きを解説し、その概念を具体的に理解するための基礎を築きます。次に、大津市玉野浦地区の経済的背景と都市計画上の位置づけを分析し、土地所有者が「開発」という選択肢に至ったであろう経済的・戦略的要因を考察します。最終的に、これらの分析を統合し、コナズ珈琲跡地の将来像を予測するとともに、地域で愛される場所の喪失と都市の発展という、現代の都市が常に直面する課題について考察を深めます。

ナフコ ツーワンスタイル 滋賀大津店:関連記事
跡地は何ができる?複数店舗が閉店!今後の展望は【コチラ】
「土地開発」の解剖学:法的・実践的入門
「土地所有者による土地開発の意向」という言葉の背後には、日本の都市計画法に根差した複雑な法制度と手続きが存在します。この表現は単なる思いつきではなく、多くの場合、綿密な計画と多額の資本投下を伴う事業の開始を告げる正式な合図です。この章では、その中核をなす概念を一つずつ解き明かしていきます。
A. 都市計画法における「開発行為」の定義
都市の無秩序な市街化を防ぎ、計画的なまちづくりを推進するために制定されたのが都市計画法です。この法律の中心的な概念の一つが「開発行為」です。
開発行為とは、簡単に言えば、建物を建てたり、特定の工作物(例:ゴルフコースなど)を建設したりする目的で、土地に物理的な変更を加える行為を指します。
具体的には、「土地の区画形質の変更」を行うことと定義されています。この「区画形質の変更」こそが、「土地開発」の実態を理解する鍵となります。
B. 土地変容の三つの柱:「区画形質の変更」
法律で定められた「土地の区画形質の変更」は、以下の三つのいずれかの行為を指し、一つでも該当すれば開発行為と見なされます 。コナズ珈琲大津店の敷地を例に、これらの概念を具体的に見ていきましょう。
「区画」の変更 – 区画整理とレイアウトの変更これは、土地の区割り、つまりレイアウトを変更する行為です。
具体的には、敷地内に新たに道路を設けたり、既存の通路を廃止・変更したり、水路や公園といった公共施設を新設・改廃することを指します 。
コナズ珈琲の広大な敷地(ナフコ、ヤマダ電機と駐車場を共有 )で大規模な再開発を行う場合、複数の建物を建設するために新たな進入路や区画道路を整備したり、現在の広大な駐車場を分割して異なる用途の区画を設定したりする行為がこれに該当します。
「形状」の変更 – 物理的な造成工事これは、土地の物理的な形、つまり地形を変更する行為です。
宅地を造成する際に行われる、坂を削って平らにする「切土(きりど)」や、窪地に土砂を盛って地盤を高くする「盛土(もりど)」が典型例です。
コナズ珈琲の跡地に、例えば高層マンションや大型商業施設を建設する場合、既存の建物を解体し、新しい建物のための深い基礎を掘削し、敷地全体を平坦に造成する工事が必要となります。これが「形状の変更」です。
「性質」の変更 – 土地利用目的の転換これは、土地の利用目的、つまりその「性質」を変更する行為です。
最も分かりやすい例は、田畑や山林といった宅地以外の土地を、建物の敷地(宅地)へと転換することです。
コナズ珈琲の敷地は既に商業地ですが、より高密度な利用を目指す再開発においては、この「性質の変更」も重要な意味を持ちます。
例えば、「低層の飲食店が一つある土地」から、「高層の共同住宅と複数の店舗からなる複合用途の土地」へとその本質的な利用形態を変えることは、広義の「性質の変更」と捉えることができます。
大規模な再開発プロジェクトでは、これら三つの変更が同時に、かつ一体的に行われるのが通常です。
新しい建物を建てる(性質の変更)ためには、土地を掘削し造成する必要があり(形状の変更)、その新しい建物へのアクセスや敷地全体の効率的な利用を考えると、道路や区画のレイアウトも見直される(区画の変更)ことになるからです。
| 変更の種類 | 法的定義 | コナズ珈琲の敷地における具体例 |
| 1. 区画の変更 | 道路、水路、公園等の公共施設の新設、変更、廃止を伴う土地の区画の変更。 | 新たな複合施設へのアクセス道路の新設、駐車場のレイアウト変更、敷地の分割。 |
| 2. 形状の変更 | 切土や盛土などの造成工事による土地の物理的な地形の変更。 | 既存建物の解体、新築物のための基礎掘削、敷地全体の地ならしや高さ調整。 |
| 3. 性質の変更 | 農地や山林など、宅地以外の土地を建築物の敷地(宅地)に変更すること。 | 低層の単一用途(飲食店)の土地から、高層の複合用途(住居+商業)の土地への利用形態の根本的な転換。 |
C. 規制プロセス:開発許可制度の存在
このような土地の利用形態を根本から変える「開発行為」は、土地所有者が自由に行えるわけではありません。都市計画区域内において一定規模以上(市街化区域では原則 1,000 平方メートル以上)の開発を行う場合、原則として都道府県知事や政令指定都市・中核市の長から「開発許可」を取得する必要があります 。大津市は中核市であるため、市長が許可権者となります。
この許可を得るためには、開発計画が道路や排水施設、防災措置といった技術的な基準を満たしているか、また、周辺の土地利用との整合性が取れているかなど、厳格な審査が行われます。
つまり、土地所有者が「開発の意向」を公にする段階では、既に事業の採算性評価、資金調達の目処、基本設計、そして行政(この場合は大津市都市計画課など )との事前協議などが水面下で進められている可能性が極めて高いのです。
人気テナントとの賃貸借契約を解除するという判断は、その開発計画が実現可能であるという高い確信がなければ下せません。したがって、「意向」という言葉は、計画が初期段階から実行段階へと移行したことを示す、重い意味を持つシグナルなのです。
ケーススタディ:玉野浦地区の戦略的価値の解放
コナズ珈琲大津店の閉店は、なぜ今、この場所で起きたのでしょうか。その答えは、玉野浦地区が持つ経済的なポテンシャルと、大津市の都市計画が描く将来像の中にあります。土地所有者の「開発の意向」は、私的な利益追求であると同時に、より大きな都市の発展戦略と共鳴する形で生まれています。
A. 経済的背景:資産として価値を高める土地
不動産、特に土地の価値は固定的ではありません。地域の発展やインフラ整備、経済状況によって変動します。大津市玉野浦地区の土地取引価格の推移を見ると、近年、地価が上昇傾向にあることが示唆されています 。
このような状況下で、土地所有者は「最高最善の使用(Highest and Best Use)」という不動産の基本原則に基づいて、自身の資産を評価し直します。これは、物理的・法的に可能で、かつ経済的に最も収益性が高くなる土地利用方法を模索する考え方です。
コナズ珈琲大津店は人気店であり、安定した賃料収入を所有者にもたらしていたと考えられます。
しかし、広大な敷地を平屋建てのカフェとしてのみ利用することは、地価が上昇した現在、もはやその土地のポテンシャルを最大限に引き出した「最高最善の使用」とは言えなくなっている可能性があります。
土地所有者は、現在の賃料収入を上回る、はるかに大きな経済的リターンを生み出す別の利用方法が存在すると判断したのです。
B. 行政のビジョン:大津市の都市再開発計画
土地所有者の私的な判断を後押ししているのが、行政が示す都市の将来像です。国土交通省が公開している資料の中には、大津市中心市街地における「市街地再開発事業案」の構想が含まれています 。この計画案は、単なる建物の建て替えにとどまらず、地域全体の活性化を目指す壮大なビジョンを描いています。
その主な目標として、
- 住宅供給を主体とした人口集積の促進
- 観光バス駐車場などを整備し、まちなかの観光・休憩拠点化
- 福祉・文化施設などの公益的機能を導入した多機能なまちづくり
などが挙げられています 。コナズ珈琲大津店が立地する土地は、ナフコやヤマダ電機といった大型店と160台規模の駐車場を共有する大規模な一団の土地です 。
このような広大な土地は、まさに上記のような複合的な市街地再開発事業を実施する上で、極めて魅力的な候補地となります。低層の商業施設が点在する現状から、高層の住宅棟と商業施設、公共的機能が一体となった拠点へと生まれ変わらせることは、大津市の都市計画の方向性と完全に一致します。
この官民のビジョンの合致は、再開発プロジェクトにとって強力な追い風となります。行政の計画に沿った開発は、開発許可の取得がスムーズに進む可能性が高いだけでなく、場合によっては補助金などの公的支援を受けられる可能性も生まれます 。
土地所有者の「開発の意向」は、こうした行政の動向を的確に捉え、民間主導でそのビジョンを実現しようとする戦略的な動きと解釈できます。
C. 土地所有者の計算:戦略的決定の構造
これらの経済的・都市計画的背景を総合すると、土地所有者の意思決定の論理が明確になります。それは、短期的な安定収入(賃貸)と、長期的かつ莫大なリターン(再開発)を天秤にかけた、合理的な経営判断です。
| 指標 | 現状:単独テナント賃貸(コナズ珈琲) | 再開発後:複合用途施設(想定) |
| 土地利用 | 低密度・単一用途(飲食店) | 高密度・複合用途(住宅、商業、公益施設等) |
| 年間収益 | 比較的安定しているが、上限がある賃料収入 | 多数の住宅・店舗からの賃料・分譲収入により大幅に増加 |
| 開発コスト | なし | 多額の初期投資(建設費等)が必要 |
| 不動産資産価値 | 土地本来の価値に依存 | 建物の価値が加わり、収益性の向上により資産価値が飛躍的に増大 |
| 都市計画との整合性 | 現状維持 | 大津市の再開発ビジョンと合致し、事業推進に有利 |
この表が示すように、再開発には巨額の初期投資というリスクが伴いますが、成功した場合のリターンは現状維持とは比較になりません。
特に、コナズ珈琲だけでなく、隣接するナフコやヤマダ電機を含む区画全体を一体的に再開発する計画であるならば、その事業規模と将来的な価値は計り知れないものになります。
コナズ珈琲の閉店は、この壮大なパズルの最初のピースが動いたことを示す、象徴的な出来事である可能性が高いのです。
共有駐車場という存在は、これらの店舗が一体の土地計画の上にあることを強く示唆しており、今回の動きが区画全体の再開発の序章であると考えるのは自然な推論です。
統合的考察と将来展望
A. なぜ閉店するのか?:要因の統合的解説
コナズ珈琲大津店の閉店に至る背景は、単一の理由で説明できるものではありません。それは、複数の強力な要因が一点に収斂した結果としての、必然的な帰結です。本レポートの分析を統合すると、その核心には以下の三つの相互に関連した力が働いていることが明らかになります。
- 土地資産価値の増大:玉野浦地区の経済的価値が向上し、土地所有者にとって、現在の低密度な利用形態(単独のカフェ)が、資産のポテンシャルを十分に活かしきれていない「機会損失」と映るようになったこと。
- 行政による再開発ビジョンの提示:大津市が、人口集積や観光拠点化を目指す市街地再開発の方向性を示したこと 。これにより、民間事業者である土地所有者は、自身の開発計画が公的な支持を得やすく、事業リスクが低減されるという確信を得たこと。
- 法的枠組みの存在:都市計画法が定める「開発行為」と「開発許可」の制度が、所有者の「意向」を具体的な建設計画へと転換するための、明確で規制された道筋を提供していること。
つまり、コナズ珈琲の閉店は、土地所有者が上昇する資産価値を最大化しようとする私的な経済合理性と、都市全体の活性化を目指す公的な都市計画のベクトルが一致した「戦略的な交差点」で起きた事象なのです。
B. 跡地の将来:根拠に基づく予測
これらの分析、特に大津市の市街地再開発事業案 に基づけば、跡地には単に別の飲食店が入るのではなく、より大規模で複合的な施設が建設されると予測するのが最も合理的です。具体的には、以下のような開発が考えられます。
- 中高層の分譲・賃貸マンション:市の目標である人口集積に直接的に貢献します。
- 低層階の商業施設:新たなレストラン、クリニック、物販店などを誘致し、地域住民の利便性を高めるとともに、新たな賑わいを創出します。
- 公共的・準公共的機能の導入:計画案にあるような福祉施設や文化施設、あるいは地域コミュニティの拠点となるスペースが設けられる可能性もあります。
この開発は、コナズ珈琲の敷地単独ではなく、隣接する大型店を含む区画全体を対象とした、長期的なプロジェクトの第一段階である可能性も視野に入れるべきです。その場合、玉野浦のこの一角は、数年をかけてその姿を大きく変え、新たな地域のランドマークとなるでしょう。
C. 広範な意味合い:都市成長における不可避な緊張関係
コナズ珈琲大津店の閉店は、多くの利用者にとって、慣れ親しんだ日常の一部が失われる寂しいニュースです。地域で愛された場所が、経済の論理によって姿を消すことへの感傷や抵抗感は、自然な感情です。
しかし、この出来事は同時に、成長を続ける都市が抱える本質的かつ不可避な緊張関係を浮き彫りにします。それは、既存のコミュニティの記憶や愛着を「保存」しようとする力と、限られた土地資源の利用を最適化し、住宅供給を増やし、都市インフラを更新しようとする「発展」の力との間のせめぎ合いです。
成功している都市ほど、土地の価値は高まり、再開発への圧力は強まります。その過程で、かつての風景は失われ、新しい風景が生まれます。コナズ珈琲大津店の物語は、大津市が活気ある成長都市であることの証左であり、その成長の過程で地域社会が経験する変化の一つの縮図と言えるでしょう。この変化を単なる「喪失」としてではなく、都市が未来に向けて自己を更新していくダイナミックなプロセスの一環として理解することが、今後のまちづくりを考える上で重要となります。
【参考文献】
- 国土交通省
- https://news.build-app.jp/article/36562/
- https://kakunin-shinsei.com/development-permit/#google_vignette
- https://www.pref.akita.lg.jp/pages/archive/363
- https://www.etod.co.jp/article/blog/157
- https://www.city.otsu.lg.jp/soshiki/035/1303/index.html