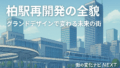日産自動車が神奈川県内に構える追浜工場(横須賀市)と湘南工場(平塚市)の閉鎖を検討しているという報道が、地域に大きな衝撃を与えています。
これに対して、地元選出の小泉進次郎元環境相も「地元で不安に思っている人はたくさんいる」と懸念を表明。
長年にわたり地域雇用と経済を支えてきた工場の存続問題は、単なる企業再編を超え、地域の暮らしそのものに直結する重大なテーマです。
本記事では、閉鎖検討の背景や今後の影響、行政や地元議員の反応、そして「工場閉鎖後の街はどうなるのか?」という視点から、街の変化を読み解いていきます。
[quads id=1]
日産が再び構造改革へ 追浜・湘南工場の閉鎖が浮上

経営再建中の日産自動車が、神奈川県内にある2つの主要拠点追浜工場(横須賀市)と日産車体 湘南工場(平塚市)の閉鎖を視野に入れているとの報道が波紋を広げています。追浜工場は1959年の操業開始以来、日産の基幹拠点のひとつとして、長年にわたって主力車種の生産を担ってきた歴史ある工場です。湘南工場もまた、日産車体の商用バンや特装車の生産を担う重要な拠点として、地元経済に深く根差してきました。
閉鎖が報じられた背景には、電動化へのシフトの遅れ、世界的なEV競争の激化、そして固定費の削減圧力があります。グローバルな競争環境の中で、日産は再建を急ぐ必要に迫られており、生産体制の最適化や非効率な工場の整理が進められているとみられます。自動車業界全体でEVや次世代技術へのシフトが進むなか、こうした構造改革は避けられない現実とも言えます。
この報道を受け、地元・神奈川11区(横須賀市など)選出の小泉進次郎衆院議員(元環境大臣)は2025年5月17日、横浜市内での記者団の取材に応じ、地域への影響について懸念を示しました。
「日産の経営が厳しいのは明らか。地元で不安に思っている人はたくさんいる」
小泉氏の発言は、単に企業の経営課題にとどまらず、地域住民の生活や未来に関わる重要な問題であるとの立場を強調したもので、今後の行政対応や企業の説明責任にも注目が集まりそうです。
小泉進次郎氏「地元の雇用を守るために国が動くべき」
小泉氏は、まだ正式な決定には至っていない段階であることを前置きしつつ、地域住民や工場従業員に不安が広がっている現状に対し、強い危機感を示しました。特に、これまで地域の中核を担ってきた工場で働く人々の生活や、地元経済への打撃を危惧していることが伝えられました。
「働いている人をはじめ、不安に思っている人を全力で守る。国を挙げて、万全のサポート体制が必要だ」
このような発言には、単に企業の判断を受け身で見守るのではなく、政府が積極的に介入し、雇用の維持や地域の活性化に向けた策を講じるべきだという強い意志が込められています。また、労働者だけでなく、その家族や周辺住民の生活の安定にも目を向ける姿勢がうかがえます。
さらに、今回の閉鎖検討がもたらす影響について、小泉氏は単なる一企業の問題では済まされないと指摘。製造業のサプライチェーンが全国に広がる現在、一次取引先のみならず、二次・三次の下請け企業や物流業者、さらには部品供給元にまで影響が波及する恐れがあると述べました。
「サプライチェーン全体に影響が及びかねない。影響は工場が立地している自治体にとどまらないだろう」
この発言からは、追浜・湘南の工場閉鎖が周辺地域だけでなく、広域的な経済ネットワーク全体に及ぼすリスクへの深い懸念がにじみ出ています。
工場閉鎖がもたらす“街の変化”とは?
今回の閉鎖検討対象となっている工場は、いずれも長年にわたり地域に雇用と経済的活力をもたらしてきた重要な拠点です。特に追浜工場は、日産の主力コンパクトカーや中型車を製造してきた実績があり、技術者や技能工が多数在籍する地域の象徴的存在でもあります。一方、湘南工場は商用バンや特装車の製造に特化しており、日産グループの中でも独自の役割を担ってきた工場です。
こうした工場が仮に閉鎖されることになれば、その影響は極めて多面的かつ深刻です。まず第一に、地元住民の雇用喪失が避けられません。工場で働く正社員だけでなく、派遣社員や期間従業員、さらには関連企業に勤務する人々も影響を受ける可能性があります。
さらに、工場周辺の経済にも波及効果が及びます。たとえば、通勤途中に利用されていた飲食店、スーパー、ガソリンスタンドなどの売上が減少し、閉店に追い込まれるケースも考えられます。結果として、地域の商圏が縮小し、経済活動が全体的に低下する恐れがあります。
また、工場関係者が転居や退職により地域を離れることで、住宅需要にも変化が起こります。空室率の上昇や住宅価格の下落といった不動産市場への影響も無視できません。特に家族で居住していた場合には、子どもの転校や転園、医療機関の利用者減少など、教育・医療インフラへの影響も生じてきます。
このように、工場閉鎖は単に企業の拠点が消えるだけでなく、雇用・消費・教育・医療といった地域生活の根幹にまで変化をもたらすものです。今後の動向次第では、自治体や民間による跡地活用の計画や、新たな企業誘致が検討されることになるかもしれません。
この問題は、神奈川県全体、さらには首都圏の産業構造や居住環境にまで波及する可能性を秘めており、まさに**広範な“まちの変化”**の象徴といえるでしょう。
[quads id=1]
まとめ:今後の注目点と対応の鍵
今回の報道をきっかけに、日産の事業再編や工場閉鎖に対する政府や自治体の対応、地域住民の受け止め方など、さまざまな側面からの注目が集まっています。追浜工場や湘南工場の閉鎖が正式に決定された場合、そのインパクトは神奈川県内にとどまらず、広域的な影響を及ぼす可能性があるため、今後の一つ一つの動きが非常に重要です。
特に、以下のような観点からの対応が焦点となるでしょう:
- 今後の正式発表の有無とそのタイミング
- 従業員に対する具体的な再雇用支援策や職業訓練の提供体制
- 跡地の具体的な活用方針(例:商業施設、集合住宅、工業団地など)
- 地域経済の再構築に向けた官民一体の長期戦略
- 教育・医療インフラの再編と地域人口の流出防止策
これらの対応が後手に回れば、地域の信頼を損なうだけでなく、さらなる経済低迷を招く恐れがあります。その一方で、行政や企業、地域住民が連携して計画的な対応を進めれば、今回の閉鎖問題は「新たなまちづくり」の契機として、より持続可能な地域社会を築くチャンスにもなり得ます。
街の変化ナビ NEXTでは、こうした一連の動きを継続的に追いかけ、読者の皆さまにとって有益でタイムリーな情報を発信し続けてまいります。未来のまちのかたちを一緒に見つめ、変化の先にある希望を探っていきましょう。
[quads id=1]